がんによって右肩が痛む仕組みとは?(基礎知識)

右肩の痛みが、必ずしも肩そのものの問題とは限らないと言われています。特に一部のがんでは、肩の筋肉や関節に直接異常がなくても痛みが出ることがあります。その背景には、体の構造と神経のつながりが深く関係していると考えられています。
まず代表的なのが横隔膜浸潤による関連痛です。肝臓がんや胆のうがんが進行すると、横隔膜に近い部位まで広がる場合があり、この横隔膜は首や肩につながる神経(主に横隔神経)と関係しています。そのため、横隔膜が刺激されると脳が「肩の痛み」として感じることがあるとされています(引用元:塩野義製薬)。
次に肺がんによる神経圧迫です。特に肺の上部に発生する腫瘍は、鎖骨の下や首から肩に走る神経の束(腕神経叢)に近接しており、腫瘍が大きくなるとこの神経を圧迫する場合があります。その結果、肩から腕にかけて痛みやしびれを感じることがあると報告されています(引用元:セルクラウド)。
さらに骨転移による痛みも見逃せません。がんが肩甲骨や上腕骨、肋骨などに転移すると、局所的な炎症や骨の破壊が起こり、動かしても動かさなくても痛みが続く傾向があるとされています。整形外科領域では、このような痛みは夜間や安静時にも悪化しやすいと説明されることがあります(引用元:もり整形外科)。
このように、右肩の痛みの背後には、横隔膜の神経反射、肺の神経圧迫、骨転移といった複数のメカニズムが存在すると考えられています。肩の痛みが長引く、安静時にも続く、鎮痛薬で改善しづらい場合は、整形外科だけでなく内科やがん専門医での相談も視野に入れることが望ましいとされています。
#右肩の痛み #がんの可能性 #横隔膜浸潤 #肺がんと肩の痛み #骨転移の症状
がん以外と見分けたい!肩こり/整形領域との違い
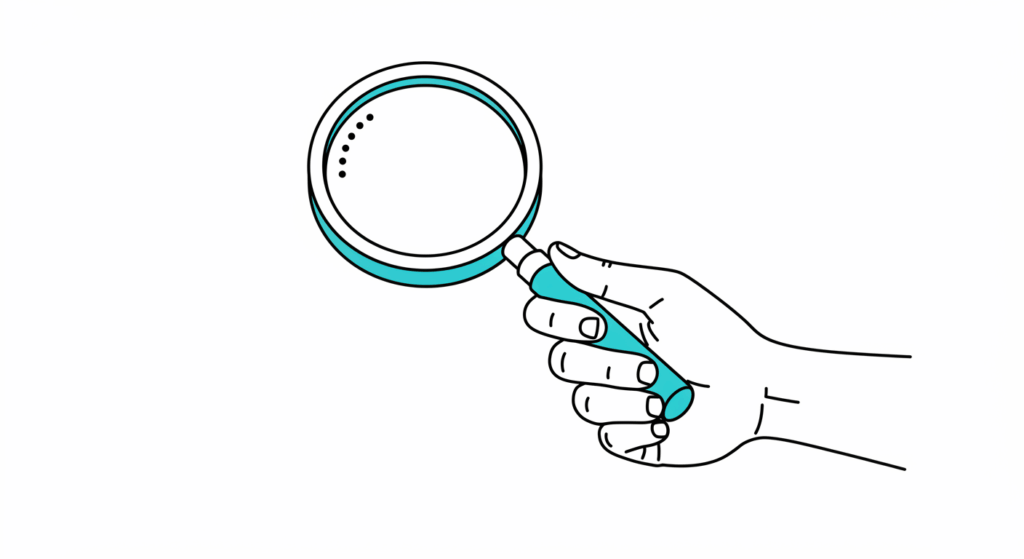
肩が痛むと多くの方は「肩こりかな」と考えがちですが、全てが同じ仕組みとは限らないと言われています。一般的な肩こりは、長時間のデスクワークや姿勢の悪さ、冷えなどによって筋肉が硬くなり、血流が滞ることで起こるとされます。この場合、マッサージやストレッチ、入浴などで血流が促されると、痛みや重だるさが和らぐ傾向があると説明されています(引用元:日本整形外科学会)。
一方で、がんが原因の肩の痛みは、性質が異なると考えられています。例えば、骨転移や腫瘍による神経圧迫では、筋肉疲労による痛みとは違い、安静時や夜間にも痛みが続くことがあるそうです。また、一般的な鎮痛薬を服用しても十分に和らぎにくいケースもあると報告されています(引用元:もり整形外科)。
さらに、がん由来の痛みでは、体を動かさなくてもジンジン、ズキズキといった鈍い痛みが続く場合があり、マッサージや温めても改善しづらいとされています。これに対し、肩こりは体を動かしたり姿勢を変えたりすると症状が軽くなることが多く、時間帯や作業内容によって強弱が出やすいのが特徴とされます(引用元:セルクラウド)。
また、がん由来の痛みでは、痛み以外にも体重減少や倦怠感、微熱など全身の変化を伴うことがあり、これらの症状が同時に出ている場合は注意が必要と言われています。もし「肩こりと思っていたら、夜も痛む」「薬を飲んでも変わらない」といった場合は、整形外科だけでなく内科やがん専門医で相談してみることが望ましいと考えられています。
#肩こりとの違い #右肩の痛み #がんの可能性 #夜間の肩の痛み #鎮痛薬が効きにくい痛み
主ながんの種類ごとの右肩痛の特徴

右肩の痛みが出る背景は、がんの種類によって異なると考えられています。それぞれのがん特有の広がり方や神経との関係が、痛みの部位や性質に影響していると言われています。
まず肝臓がんの場合です。肝臓は横隔膜のすぐ下に位置しており、がんが進行すると肝臓の外側を覆う被膜が引き伸ばされることがあります。この被膜の刺激が横隔膜を通じて横隔神経に伝わり、右肩に「関連痛」として感じられることがあるとされています(引用元:シオノギウェルネス)。右わき腹の鈍痛や圧迫感と併せて出現することも多いと説明されています。
次に肺がんです。特に肺の上部(肺尖部)にできる腫瘍は、鎖骨の下から肩や腕にかけて走る腕神経叢の近くに位置しています。腫瘍が大きくなると神経を圧迫し、肩から腕、時には背中にかけて広がる痛みやしびれを引き起こす場合があると言われています。また、リンパ節が腫れることで神経や血管が圧迫され、痛みの増強や可動域の制限につながることもあるそうです(引用元:マイクロCTC検査、シオノギウェルネス)。
さらに骨転移による右肩痛もあります。乳がん、肺がん、肝臓がんなど複数のがん種で見られる可能性があり、肩甲骨や上腕骨、肋骨などに転移すると局所の炎症や骨の破壊によって強い痛みが生じると報告されています。この痛みは動かさなくても続き、夜間や安静時に悪化しやすいとされます。また、神経や血管への影響でしびれや感覚異常を伴うこともあるそうです(引用元:もり整形外科)。
このように、右肩の痛みは原因となるがんの種類や部位によって特徴が異なると考えられています。痛みの性質や併発症状を丁寧に観察することが、早期の来院や検査のきっかけにつながると言われています。
#右肩の痛み #肝臓がん #肺がん #骨転移 #関連痛
こんな症状があったら要注意!併発症状と受診の目安
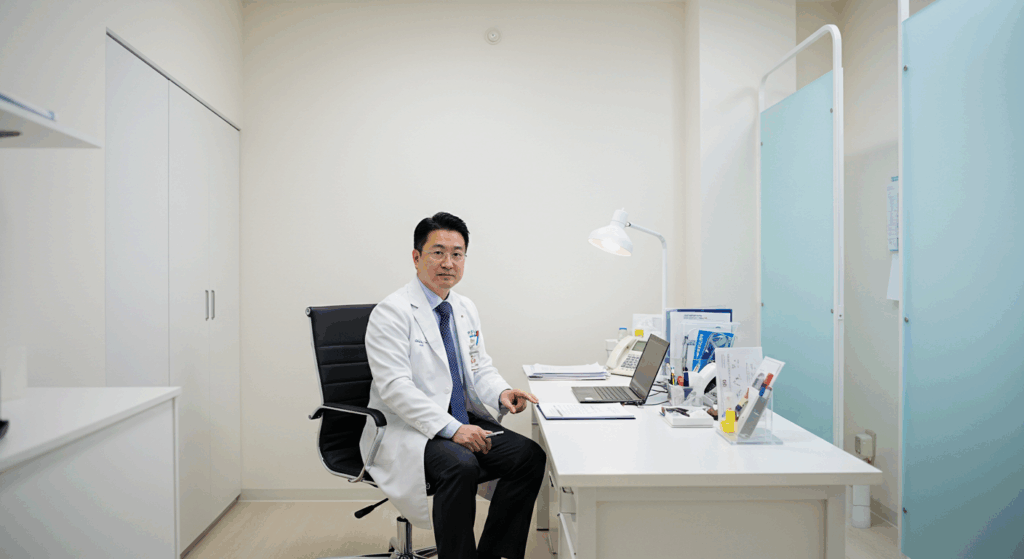
右肩の痛みだけでなく、他の症状が同時に出ている場合は注意が必要と言われています。例えば、手や腕のしびれ、理由のない体重減少、微熱や発熱、息切れなどは、単なる肩こりや筋肉疲労では説明しづらいことが多いとされます。こうした全身の変化は、がんや他の重大な病気と関係している可能性があるため、軽視しないほうが良いと言われています(引用元:もり整形外科)。
痛みの性質にも注目が必要です。がんに関連する痛みでは、動かさなくてもズキズキと続き、安静時や夜間に悪化する傾向があると報告されています。また、一般的な鎮痛薬を使っても十分に和らぎにくい場合があるとも説明されています。こうした特徴は、筋肉由来の肩こりとは異なるため、見極めのポイントになると考えられます(引用元:もり整形外科)。
実際の相談例として、「肝臓がんステージ3の父が、右肩と右脇腹に痛みを訴えている」というケースがあります。この場合、肝臓の被膜伸展や横隔膜への影響で右肩に関連痛が生じている可能性が指摘されています(引用元:シオノギウェルネス)。相談内容からは、痛みが強く生活に支障をきたしていること、夜間も痛みが持続していることから、セルフケアだけで様子を見るのではなく、早めに医療機関に来院することが望ましいと考えられます。
特に、痛みが急激に強くなったり、呼吸困難や高熱、吐き気などが併発した場合は、救急外来の受診も検討されるべきだと言われています。日々の体調の変化を記録し、症状の経過を医師に伝えることで、より適切な検査や対応につながると考えられています。
#右肩の痛み #がんのサイン #併発症状 #夜間痛 #受診の目安
まとめ&対応策:まず何をすべき?専門医への相談準備
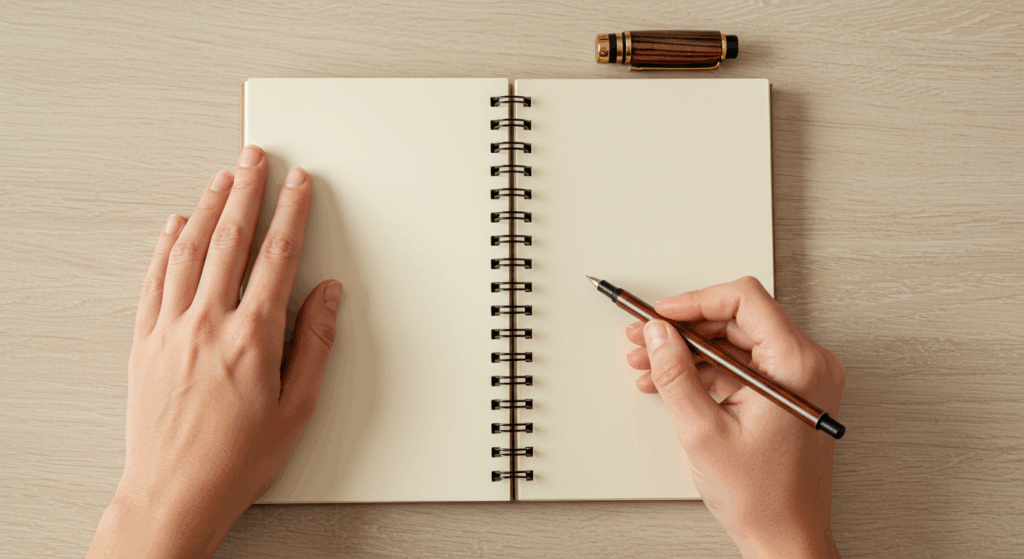
右肩の痛みが続く場合、まずは日々の症状を客観的に記録することが大切と言われています。痛みが出る時間帯、持続時間、動作や姿勢との関係、夜間の有無、鎮痛薬の効果などをメモに残しておくと、来院時の説明がスムーズになります。また、体重や発熱、しびれなどの併発症状もあわせて記録すると、診察の手がかりになりやすいと考えられています(引用元:もり整形外科)。
受診先としては、肩そのものの病変が疑われる場合は整形外科、内臓や呼吸器に関わる症状がある場合は消化器内科や呼吸器内科が候補になります。いずれも痛みの原因を見極めるために必要な検査を行える医療機関を選ぶことが望ましいとされています(引用元:シオノギウェルネス)。
医師との相談をより有意義にするため、事前に質問を整理しておくことも役立つと言われています。例えば、以下のような質問が参考になります。
- 「夜間も痛みが続きますか?」
- 「動かさなくてもズキズキしますか?」
- 「鎮痛薬でどの程度変化がありますか?」
- 「痛み以外にしびれや発熱はありますか?」
- 「画像検査は必要でしょうか?」
こうした質問リストは、医師に症状の特徴を具体的に伝える助けになります。さらに、記録した情報と合わせて提示することで、より正確な触診や検査につながる可能性が高まると考えられています。
早い段階での来院が重要だと言われていますので、「様子を見る」だけで時間を過ごさず、不安があるうちに専門医へ相談する行動が推奨されています。
#右肩の痛み #受診準備 #症状記録 #質問リスト #専門医相談









