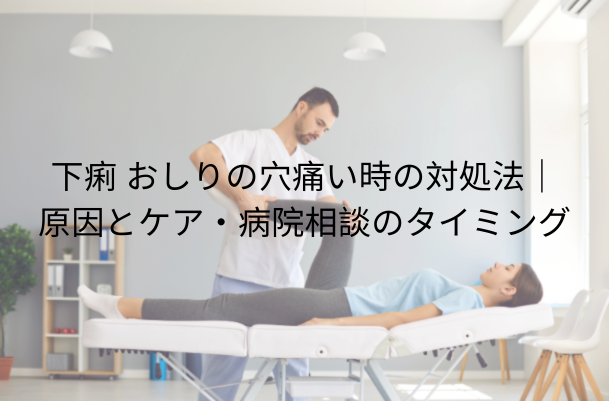下痢でおしりが痛くなる理由と仕組み

下痢による肛門部への物理的刺激
下痢になると、通常よりも排便回数が増え、便が水分を多く含んでいるため勢いよく流れ出やすくなります。この状態が続くと、肛門周囲の皮膚や粘膜が何度も擦れ、炎症や刺激を受けやすくなると言われています(引用元:ubie.app)。特に下痢便はアルカリ性寄りになることがあり、皮膚への刺激が増してヒリヒリ感や痛みを生じやすいそうです。加えて、トイレットペーパーで繰り返し強く拭くことも、皮膚バリアを傷つける原因のひとつになるとされています。
裂肛(切れ痔)との関係
下痢によって肛門が痛くなる理由の一つに**裂肛(切れ痔)**があります。これは肛門の皮膚や粘膜に小さな傷ができる状態で、勢いよく排出された下痢便が擦過することで発生しやすいと言われています(引用元:brand.taisho.co.jp)。裂肛は排便時に鋭い痛みを伴うことが多く、便の刺激や筋肉の緊張によって症状が長引くケースもあるそうです。
皮膚炎や湿疹の影響
下痢が長引くと、肛門周囲の皮膚に炎症が起こり、肛門周囲皮膚炎になることもあります。これは便中の成分や湿気、摩擦によってかゆみやヒリつきを伴い、場合によっては赤みやただれが生じることもあると言われています。さらに、排便後にしっかり洗い流さずにいると刺激物が残り、炎症を悪化させる可能性があるそうです。
痛みが強い場合に考えられること
痛みが排便時だけでなく、座っているときや歩行時にも続く場合は、裂肛以外の病気が関与していることもあります。例えば痔核(いぼ痔)の炎症や、肛門周囲膿瘍といった感染性の病変です。こうしたケースでは、早期に医療機関での確認が望ましいとされています(引用元:kajigaya-clinic.com)。
#下痢でおしり痛い
#裂肛の原因
#肛門周囲皮膚炎
#便の刺激と痛み
#下痢と肛門トラブル
主に考えられる疾患とサイン
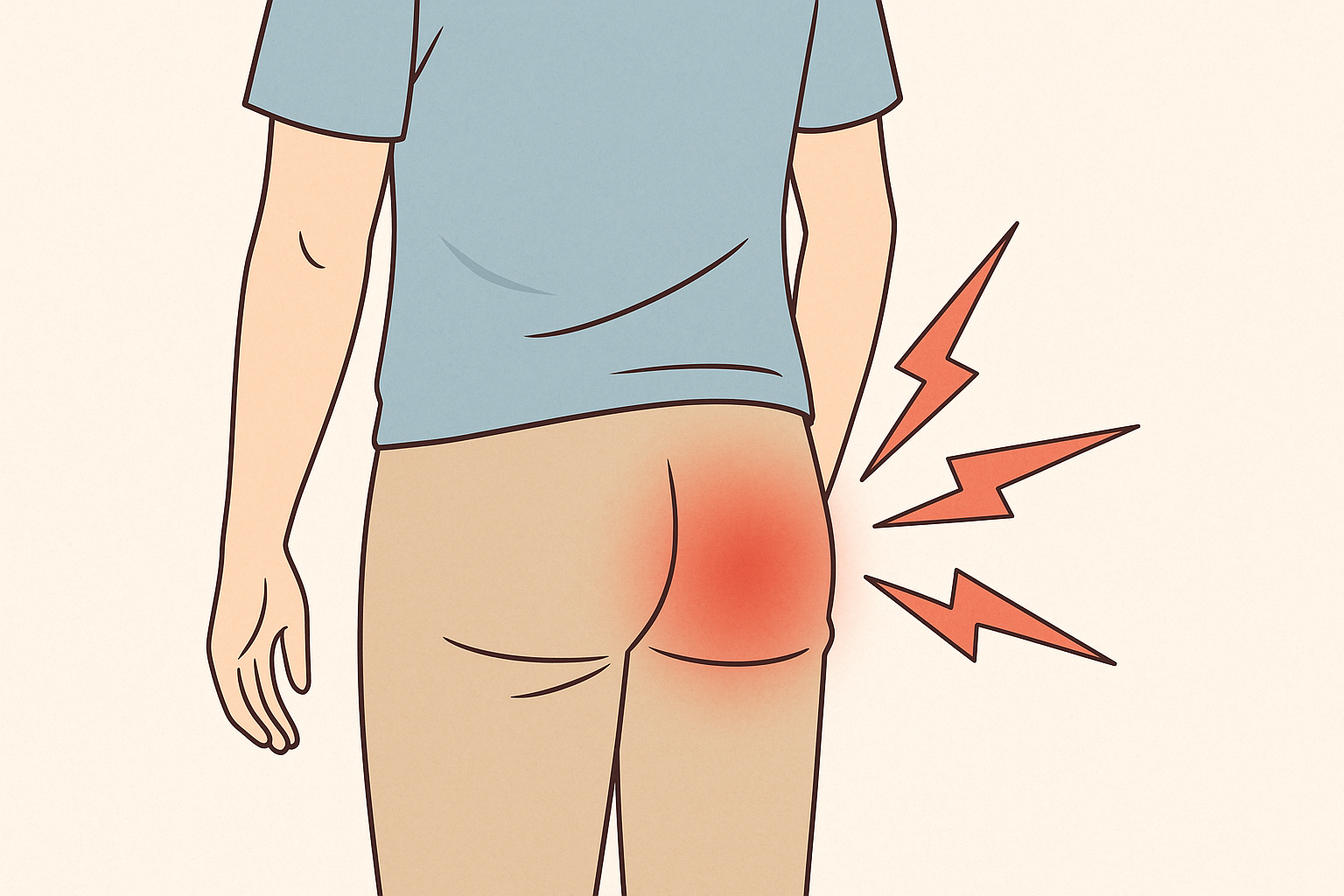
裂肛(切れ痔)
下痢の勢いで肛門の皮膚や粘膜が傷つき、鋭い痛みを感じる状態を**裂肛(切れ痔)**と言います。排便時にキューっと締め付けられるような痛みが走り、その後もしばらくヒリヒリ感が残ることがあるそうです。また、便やトイレットペーパーに少量の鮮血が付く場合もあります(引用元:brand.taisho.co.jp)。下痢と便秘を繰り返す人や、肛門括約筋が緊張しやすい人に発生しやすいと言われています。
痔核(いぼ痔)
**痔核(じかく)**は、肛門周囲の血流が滞って腫れやしこりができる状態です。外痔核では排便時や座位で強い痛みが出ることがあり、内痔核では初期は痛みが少なくても、炎症や血栓ができると急激に痛みが増すことがあります(引用元:kajigaya-clinic.com)。下痢や長時間のいきみが発症の引き金になることもあるそうです。
肛門周囲膿瘍・痔ろう
肛門周囲膿瘍は、肛門の内部から細菌が侵入し、膿がたまって腫れる病気です。熱感や発赤、発熱を伴うこともあり、歩行や座位が困難になるほどの痛みを引き起こすケースもあるとされています(引用元:ino8550.jp)。放置すると膿の出口が皮膚側にできてしまい、痔ろうに進行する場合があるため注意が必要です。
炎症性腸疾患
下痢と肛門痛が長期間続く場合、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患が関わっていることもあります。これらは腸全体の炎症が肛門部にまで影響を及ぼし、腫れや痛みを伴うことがあると言われています。加えて血便や発熱、全身のだるさなどを併発する場合もあります。
#下痢と裂肛
#痔核の症状
#肛門周囲膿瘍
#痔ろうの進行
#炎症性腸疾患と肛門痛
自宅でできる対処法とケアポイント

肛門周囲をやさしく清潔に保つ
下痢によるおしりの痛みを和らげるには、まず刺激を減らすことが大切と言われています。排便後はトイレットペーパーで強くこすらず、軽く押さえるようにして拭き取ります。可能であれば、ぬるま湯で洗い流すか、ウォシュレットを弱めの水圧に設定して短時間で使うと良いそうです(引用元:ubie.app)。その後はやわらかいタオルで軽く押さえて水分を取り、湿った状態を放置しないことがポイントです。
温めて血流を促す
肛門周囲の血流が悪くなると炎症や痛みが長引くことがあるため、温めるケアが役立つ場合があります。具体的には、ぬるめのお湯に5〜10分ほど浸かる「座浴」や、温かいタオルを当てて保温する方法があります(引用元:kajigaya-clinic.com)。ただし、膿や強い腫れがある場合は温めで悪化することもあるため、自己判断せず症状に応じて行うことが望ましいです。
刺激物や冷たい飲食を控える
香辛料やアルコール、冷たい飲み物は腸を刺激し、下痢や肛門の痛みを悪化させることがあると言われています。症状が落ち着くまでは、消化の良い食事や温かい飲み物を中心にするのがおすすめです。特に食物繊維の中でも水溶性食物繊維(バナナ、リンゴ、煮た野菜など)は便の形を整えやすいとされています。
肛門周囲を乾燥させすぎない
清潔に保つことは大切ですが、洗いすぎや乾燥しすぎも皮膚のバリア機能を低下させる原因になるとされています。必要に応じてワセリンなどの保護剤を薄く塗ることで、摩擦や刺激を和らげられることがあります(引用元:brand.taisho.co.jp)。
#下痢ケア方法
#肛門の清潔習慣
#温浴で血流促進
#食事で下痢予防
#摩擦対策と保護ケア
症状が続く・悪化する場合に考える治療法
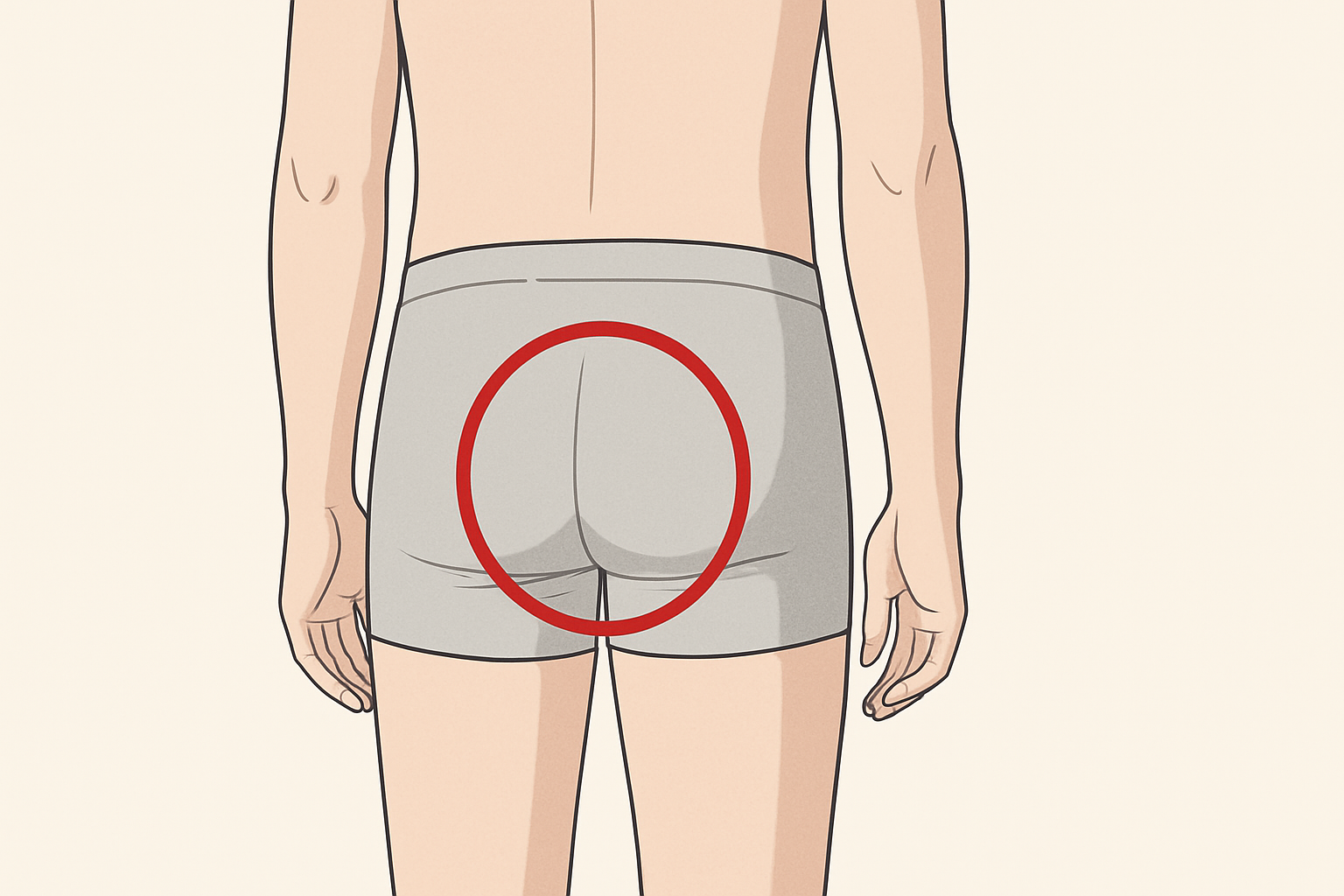
保存療法での対応
下痢によるおしりの痛みが長引く場合、まずは保存療法と呼ばれる比較的負担の少ない方法が検討されると言われています。裂肛や軽度の痔核では、炎症を抑える軟膏や坐薬が処方されることがあり、排便時の痛みや腫れの軽減をサポートします(引用元:brand.taisho.co.jp)。また、腸内環境を整えるための整腸剤や食事指導が併用されることもあります。こうした治療は自宅でのケアと並行して行うことで効果が出やすいとされています。
炎症や感染への対応
肛門周囲膿瘍など細菌感染が疑われる場合は、抗菌薬の投与や排膿処置が行われることがあるそうです(引用元:ino8550.jp)。放置すると痔ろうに進行する可能性があるため、腫れや熱感、発熱を伴うときは早めの来院が望ましいとされています。場合によっては局所麻酔下で膿を排出し、感染源を取り除く処置が必要になることもあります。
手術的治療の選択肢
重度の痔核や再発を繰り返す裂肛、進行した痔ろうなどでは、手術的治療が検討されることがあります。痔核切除術やゴム輪結紮術、裂肛の括約筋部分切開、痔ろうの根治術などが代表例です(引用元:kajigaya-clinic.com)。ただし、これらは症状や全身状態、生活背景を考慮した上で選ばれるため、自己判断せず専門医と相談して進めることが推奨されています。
再発予防への取り組み
治療が終わっても、生活習慣を見直さなければ再発する可能性があると言われています。規則正しい排便リズムを保ち、下痢や便秘を防ぐ食事管理、水分補給、適度な運動などを習慣化することが、長期的な予防につながります。
#下痢と肛門痛治療
#保存療法と薬物ケア
#感染症対応
#肛門手術の選択肢
#再発予防習慣
病院受診すべきサインと受診先の目安

強い痛みや長引く症状
下痢に伴うおしりの痛みが数日経っても改善せず、むしろ悪化している場合は、早めの来院が望ましいと言われています。特に、排便以外の時間でも持続的な痛みがある、夜眠れないほどの違和感が続く場合は、裂肛や痔核、肛門周囲膿瘍など進行性の病気が関与している可能性があります(引用元:kajigaya-clinic.com)。
腫れや発熱を伴う場合
肛門周囲の腫れ、触ると熱を感じる、全身に発熱がある場合は、肛門周囲膿瘍や感染症が疑われることがあります(引用元:ino8550.jp)。このような症状は放置すると痔ろうへ進行する可能性があるため、自己判断せず受診することが重要とされています。
出血の量や性質に注意
排便時に鮮血が大量に出る、または便に混ざっている血が増えてきている場合は、痔核や裂肛以外に大腸ポリープや炎症性腸疾患が背景にあることもあります(引用元:brand.taisho.co.jp)。少量の出血でも繰り返す場合は検査を受けることが望ましいです。
受診先の目安
肛門の痛みや腫れが中心であれば肛門科や肛門外科、消化器内科が適しています。下痢が長引く、腹痛や全身症状を伴う場合は、消化器内科や総合診療科での検査が推奨されます。受診時には症状の経過や生活習慣、下痢の回数や性状をメモして持参すると、触診や検査がスムーズに進むと言われています。
#下痢と肛門痛受診目安
#腫れと発熱の注意サイン
#肛門周囲膿瘍の可能性
#出血時の受診判断
#適切な診療科選び