体のしびれが続くと不安になるもの。この記事では、よくある原因から受診の目安、セルフケアの注意点まで、わかりやすく解説します。
体のしびれとは?|よくある症状とその特徴

ピリピリ、ジンジン…どんな感覚が「しびれ」?
しびれという言葉を聞くと、まず思い浮かぶのは「ピリピリ」や「ジンジン」といった感覚ではないでしょうか。実際にはそれだけでなく、「ビリビリ」「ムズムズ」「感覚が鈍い」「触れているのに気づきづらい」といったバリエーションがあります。中には「触れていないのに触られているような感じがする」というように、違和感が強く出るケースもあります。
しびれは神経に関わる症状のひとつとされていて、皮膚の感覚を伝える神経に異常がある場合に起こりやすいと言われています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/200827-002-QK)。そのため、しびれの出方は原因や部位によってかなり異なることがあります。
会話の中でも「このしびれ、ちょっといつもと違うかも…」と気になったことがある方も多いはず。しびれの感覚は自分の体の中で起きている異変を知らせるサインのようなもので、見過ごさないことが大切です。
一時的なしびれと慢性的なしびれの違い
一時的なしびれは、長時間の正座や腕枕などで神経や血管が一時的に圧迫されたときに起こるものです。たとえば「足がしびれたけど立ち上がったらすぐ治まった」というようなケースですね。こうした場合、血流が戻ると感覚も回復していくため、特に心配はいらないと考えられています。
一方で、慢性的なしびれは数日〜数週間以上続くもので、原因によっては医療機関での相談が推奨されています。とくに「左右どちらかだけがしびれる」「手や足の先から徐々に広がっている」「しびれとともに力が入りづらい」といった症状は、頚椎症や脳梗塞、糖尿病による末梢神経障害などが関与している可能性もあると言われています(引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html、https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_645.html)。
慢性的なしびれに対して「そのうち良くなるだろう」と放置してしまうと、改善までに時間がかかることもあるため、気になる場合は早めに相談することが望ましいとされています。
#体のしびれ
#一時的なしびれ
#慢性的なしびれ
#神経の異常
#感覚異常
体のしびれの主な原因とは?
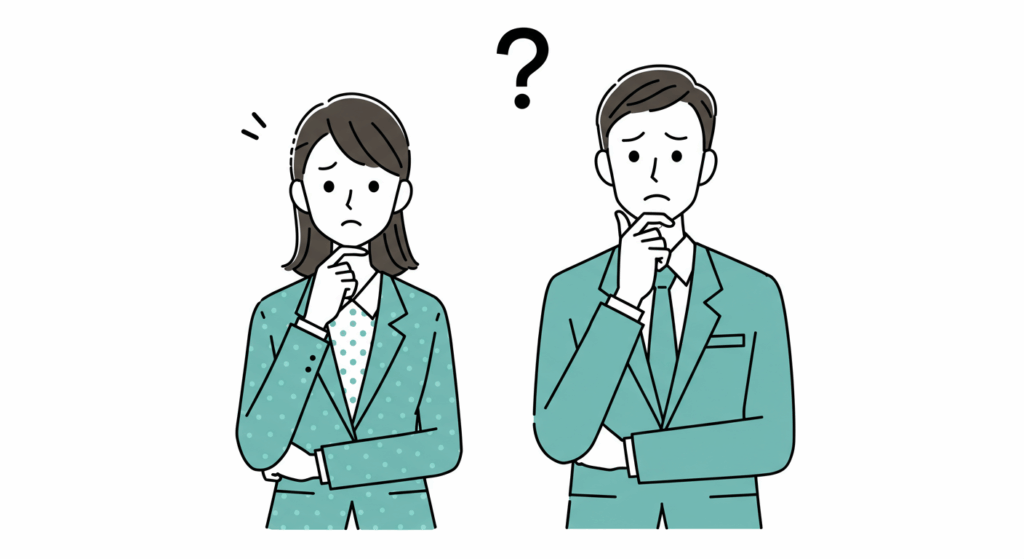
神経の圧迫や血流障害(例:頚椎症・腰椎ヘルニア)
しびれの原因としてよく知られているのが、神経が圧迫されている状態です。たとえば首の骨(頚椎)や腰の骨(腰椎)の間にある椎間板が変性して飛び出す「椎間板ヘルニア」は、その代表的なものとされています。とくに「頚椎症」や「腰椎椎間板ヘルニア」では、手足の末端までしびれを感じることがあるようです。
また、長時間同じ姿勢で座っていたり、脚を組んだ状態が続いたりすると、一時的に神経や血管が圧迫されてしびれを感じることがあります。これらは「血流の滞り」が関係していると考えられており、圧迫がなくなれば自然に回復していくこともあります(引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html)。
ただし、圧迫が慢性的に続くと、神経への影響が長引くこともあるため注意が必要です。しびれと同時に力が入りづらくなったり、感覚が鈍くなったりする場合は、専門的なチェックが勧められています。
生活習慣や姿勢の悪さによるもの
毎日の生活の中に潜む「小さなクセ」が、しびれの原因につながるケースもあります。たとえば、パソコン作業中に肩が前に出て猫背になっていると、首から肩、腕にかけての神経に負担がかかりやすくなると言われています。スマホを長時間使ってうつむいている姿勢も同様です。
こうした日常的な体の使い方によって、筋肉が緊張し、神経や血管を圧迫してしまうことがあります。これが慢性的なしびれにつながる可能性があるため、姿勢の改善や適度なストレッチが効果的だとされています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/%E5%AF%9D%E8%B5%B7%E3%81%8D%E3%81%AB%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%E6%89%8B%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%B3%E3%82%8C%E3%82%84%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB/)。
生活習慣の見直しは、すぐに変化が出るわけではないですが、積み重ねが大きな差になることもあるようです。
脳・脊髄・糖尿病などの内科的疾患の可能性
体のしびれは整形外科的な原因だけでなく、内科的な病気が関係していることもあります。とくに注意が必要なのが、脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脳腫瘍などの「中枢神経」に関わる病気です。片側の顔や手足がしびれる場合は、早めに医療機関に相談することが推奨されています(引用元:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_645.html)。
また、糖尿病が原因で起こる「糖尿病性末梢神経障害」も、しびれの一因として知られています。高血糖状態が続くことで神経がダメージを受け、足の指先や手の先にしびれを感じるケースがあるようです。これは徐々に進行していくことが多く、自覚症状が出た時には既に進んでいることもあるとされています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/200827-002-QK)。
このように、しびれは体からの重要なサインのひとつ。症状の出方や頻度によっては、整形外科ではなく内科・神経内科の分野での検査が必要になることもあるようです。
#体のしびれ
#頚椎症
#生活習慣としびれ
#糖尿病としびれ
#血流障害
こんなときは病院へ|受診の目安と診療科の選び方

しびれが続く・広がる・片側だけ…危険なサインとは
「たまに手がしびれるけど、大したことないよね」と感じている方も多いかもしれません。ですが、しびれが何日も続いたり、日々広がっていくような場合は、注意が必要だと言われています。特に、「片側の手足だけがしびれる」「力が入りにくくなる」「顔の半分も一緒に感覚がおかしい」などの症状は、脳や神経系に関わる病気の可能性があるとされており、早めの対応が勧められています(引用元:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_645.html)。
また、しびれと一緒にめまいや言葉のもつれ、ふらつきなどが出た場合も、すぐに医療機関へ相談したほうがよいとされています。こうした症状は一見日常的なものに感じられるかもしれませんが、命に関わる病気の初期サインであることもあると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/200827-002-QK)。
違和感を感じた段階で「まだ大丈夫」と思い込まず、早めに対処することで、後悔のない選択につながるかもしれません。
整形外科?神経内科?迷ったときの受診科の選び方
「このしびれ、どこで診てもらえばいいの?」と迷う方は少なくありません。たとえば、首や腰の痛みとセットで手足がしびれる場合、まず整形外科での相談が一般的とされています。これは、頚椎や腰椎の神経圧迫によるものが多いためだと考えられています。
一方、しびれが急に起きたり、左右どちらかだけだったり、顔や言葉にも影響が出ていると感じたときは、神経内科や脳神経外科といった専門科での検査が必要とされています(引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html)。
また、糖尿病などの持病がある方は、内科的な検査も選択肢に入れておくとよいでしょう。しびれの原因は複雑なケースも多く、必要に応じて複数の診療科を紹介されることもあります。最初の来院先に迷った場合は、かかりつけ医に相談するのも一つの方法です。
診察の流れと伝えておくべき症状のポイント
初めて来院する場合、どうやって自分の症状を伝えればいいのか不安になる方もいると思います。しびれの相談では、次のような点を伝えることが大切だとされています。
- どの部位に、どのようなしびれがあるか(例:右手の親指から中指にかけてピリピリする)
- しびれが始まった時期やタイミング(例:1週間前から毎朝)
- きっかけがあったかどうか(例:荷物を持ってから、転倒してから など)
- 他に気になる症状(例:力が入りにくい、歩きづらい、痛みを伴う など)
こうした情報があると、医師が原因を特定しやすくなるとされています。場合によってはMRIや血液検査、神経伝導検査などを行うこともあり、正確な情報が後の対応につながります(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/)。
来院の際には、可能であればメモを持っていくと伝え漏れを防ぎやすく、安心感にもつながります。
#体のしびれ
#医療機関への相談
#整形外科と神経内科
#片側のしびれ注意
#受診前にまとめること
体のしびれを和らげる日常ケアと予防法
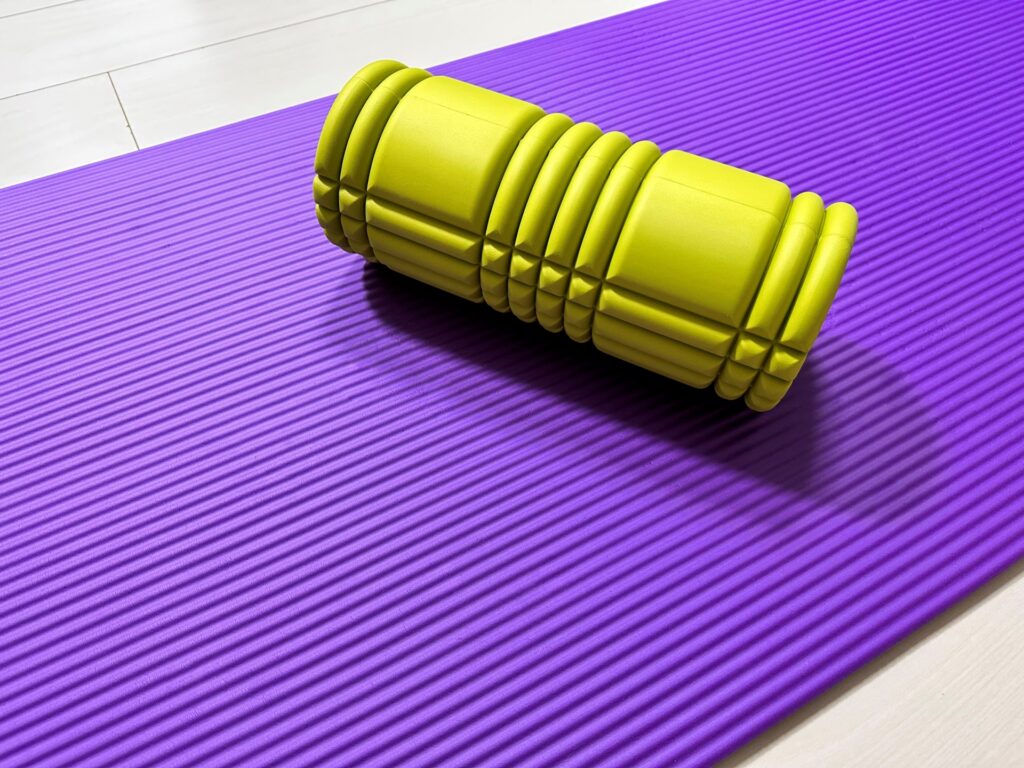
ストレッチや体勢改善で血流をサポート
しびれを感じやすい方にとって、日々の姿勢や筋肉の緊張状態は見逃せないポイントです。とくに首や肩まわり、腰周辺の筋肉が固まってしまうと、神経や血管が圧迫されやすくなり、しびれにつながると言われています。こうした背景から、軽いストレッチや体をほぐす動きがしびれの軽減に役立つと考えられています(引用元:https://takeyachi-chiro.com/寝起きに起こる手のしびれや痛みの原因と絶対に/)。
肩をゆっくり回したり、手首や足首を動かすなどの簡単な体操をこまめに取り入れることで、血流の改善につながる可能性があるようです。また、立ち上がって姿勢をリセットする習慣を持つことも、神経への圧迫を防ぐひとつの工夫です。
長時間同じ姿勢が続いていたら、「ちょっと伸びをしようかな」と体に声をかけるくらいの感覚が大切です。
デスクワーク・スマホ時の注意点
現代人にとって、パソコンやスマホの長時間使用は避けづらいものです。ただ、それによって無意識のうちに首や手首、腰などが緊張し、神経が圧迫されやすくなる状況が生まれるとも言われています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/200827-002-QK)。
とくにスマホを見るときに首が前に出て「ストレートネック」気味になっていたり、マウスを操作し続けて手首が下がっている状態などは、しびれにつながることもあるようです。作業の合間に画面を見る位置を調整したり、椅子と机の高さを見直すことも大切です。
また、利き手ばかり使って負担が偏っていないか、時々意識してみることも体へのやさしさにつながります。自分なりのリセットポイントを作っておくのも、予防のひとつかもしれません。
サプリや入浴などの補助的ケア(※効果の限界も明記)
しびれ対策として、ビタミンB群のサプリメントや温熱療法を取り入れる方も増えているようです。特にビタミンB1やB12は神経の働きをサポートする栄養素とされ、意識的に摂取されるケースも見られます(引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-037.html)。
また、湯船に浸かって全身を温めることで血流を促すことも、しびれの軽減に役立つ可能性があると考えられています。冷えが気になる方は、足湯などから始めても良いかもしれません。
ただし、こうした方法はあくまで「補助的なケア」であり、根本的な原因にアプローチできるものではないとも言われています。症状が長引く場合は、自己判断だけに頼らず専門家へ相談することが勧められています。
#しびれ予防
#ストレッチ習慣
#デスクワーク対策
#温めケア
#ビタミンと神経サポート
まとめ 体のしびれを軽く見ず、早めの対応を

まずは症状の見極めが大切
体のしびれは、多くの人にとって身近な違和感かもしれません。長時間の同じ姿勢や、ちょっとした疲れで起こることもあるので、「放っておけば消えるだろう」と思ってしまいがちです。けれども、しびれの奥には神経や血流、内科的な病気など、思いもよらない原因が隠れていることもあると指摘されています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/200827-002-QK)。
「いつものしびれとは少し違うな」「時間が経ってもしびれが引かないな」と感じたら、まずはその症状の出方や頻度、場所などを記録してみるのがおすすめです。言葉で説明するのが難しい感覚だからこそ、自分の体の状態を冷静に整理することが大切だとされています。
気になる違和感は、「年齢のせいかな」で済ませずに、まずは見極めてみることが予防にもつながります。
「おかしい」と感じたら医療機関へ相談を
体からのサインを見逃さないことが、早期対応への第一歩だとされています。特に、しびれが片側だけだったり、顔や言葉、視力などにも変化がある場合は、早めの相談が勧められています(引用元:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_645.html)。
また、力が入りづらくなる、しびれと同時に痛みや感覚異常が出る、といったケースも「神経のトラブルかもしれない」と考えておいたほうがよいようです。すべての症状が重篤な原因と結びついているわけではありませんが、「おかしい」と思ったタイミングで医療機関を頼ることが、安心への近道になるかもしれません。
初めて相談する場合には、「いつから・どこが・どんなふうにしびれるか」「他に変わったことがあるか」などの情報をメモして持参すると、スムーズに伝えやすくなります。早めに動くことで、長引く不安を減らせる可能性もあると考えられています。
#体のしびれ対策
#医療相談の目安
#症状の見極め方
#片側しびれは要注意
#不調の早期対応









