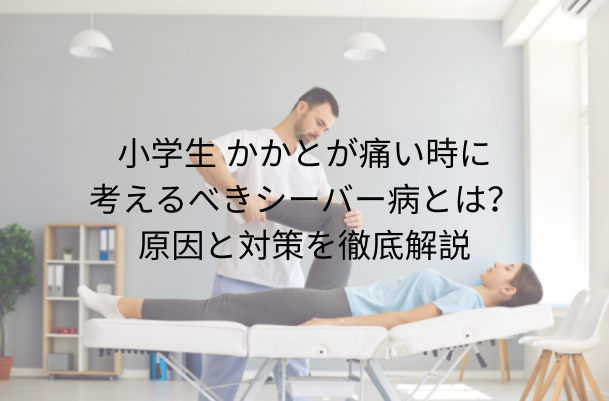小学生のかかと痛は見逃せないサイン:シーバー病の基礎知識

「成長痛だからそのうち治る」は間違いかも?
小学生のお子さんが「かかとが痛い」と訴えたとき、「成長痛かな?」と軽く考えてしまうこともあるかもしれません。
確かに成長期には体が急激に伸びることで、膝や踵に痛みが出やすい時期があります。しかし、もし運動時や練習後にかかとを押さえてうずくまるような痛みが繰り返し出る場合は、単なる成長痛ではなく「シーバー病(踵骨骨端症)」というスポーツ障害の可能性があるとも言われています【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/】。
シーバー病は、かかとの骨(踵骨)の成長軟骨が炎症を起こすことで痛みが出る疾患で、特にサッカーやバスケットボール、野球など、ジャンプやダッシュを繰り返すスポーツをしている小学生男子に多くみられるとされています。
シーバー病は「成長期特有の疲労骨端症」
このシーバー病は、正式には踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう)と呼ばれ、踵の骨が完全に成長する前の時期に起こることが特徴です。
運動によってアキレス腱が引っ張る力が加わることで、かかとの骨の軟骨部分に負荷がかかり、炎症を引き起こすと考えられています。
「ジャンプの着地時に痛む」「踵をつけて歩くと痛いのでつま先立ちになる」「運動後に痛みが強くなる」などが典型的な症状と言われています。
痛みを無理に我慢して運動を続けると、悪化するケースも報告されていますので、早期の気づきと対応が重要になるようです。
シーバー病はレントゲンでは異常が出にくい場合もあるため、症状の出方や運動歴などを基に整形外科で触診や経過観察を行うのが一般的とされています。
#小学生かかと痛い
#シーバー病とは
#踵骨骨端症
#スポーツ障害
#成長期の足トラブル
主な症状チェックと見分けポイント

シーバー病に特徴的な症状とは?
「小学生がかかとを痛がるときに考えられる症状」として、シーバー病(踵骨骨端症)が挙げられます。
このシーバー病では、運動中や運動後にかかとがジンジン痛むのが大きな特徴です。特にジャンプやダッシュ動作の後、踵を押さえてうずくまる姿を見かけたら注意が必要かもしれません。
また、「踵をつけて歩くと痛いため、つま先立ち歩きをしている」「踵を軽く押すと痛がる」という点も、よく見られる症状として知られています【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/】。
痛みの出方は日によって強さが変わることもありますが、基本的に安静にしている時は痛みが落ち着く傾向があるようです。
成長痛との違いは「痛む場所」と「動作時の痛み」
シーバー病とよく混同されるのが「成長痛」ですが、両者にはいくつかの違いがあると言われています。
成長痛は夕方から夜間にかけて、膝や太ももの周辺が痛くなることが多く、翌朝にはケロッとしている場合がほとんどです。
一方、シーバー病は踵のピンポイントに痛みが出ることが特徴で、運動時や運動後に痛みが強くなる傾向があります。
さらに、「踵を押すと痛い」という明確な圧痛ポイントがある場合、シーバー病の可能性が高いとされています。
放置してしまうと悪化のリスクも
「そのうち治るかな」と放置していると、症状が長引いたり、無理な動きで悪化させてしまうケースもあるため、注意が必要です。
痛みが出ているときは、無理に運動を続けず、早めに専門家に相談することが重要だと言われています。
#シーバー病チェック
#かかとが痛い
#成長痛との違い
#早期発見が大切
#症状セルフチェック
まずできるセルフケアと応急処置方法

痛みが出たら「無理をしない」ことが最優先
シーバー病(踵骨骨端症)の場合、痛みを我慢しながら運動を続けることは悪化のリスクにつながると言われています。
「少し痛いけど頑張れる」と思ってしまうお子さんも多いですが、まずは無理に動かさず安静を保つことが大切です。
数日間、運動を控えるだけでも症状が軽くなることが多いとも言われています【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/】。
アイシングで炎症を抑える
運動後や痛みが強いときには、かかと周辺を冷やすアイシングも効果的とされています。
ビニール袋に氷と水を入れてタオル越しに10〜15分冷やすことで、炎症の広がりを防ぐと言われています。
ただし、冷やしすぎによる凍傷には注意が必要ですので、適度な時間で行いましょう。
ストレッチとマッサージで負担を軽減
アキレス腱やふくらはぎ、足底の筋肉が硬くなると、踵への負担が増えてしまいます。
そのため、ふくらはぎのストレッチや、足裏をテニスボールなどでほぐすマッサージを日常的に取り入れると、かかとへの負担が和らぐとも考えられています。
また、土踏まずのアーチが崩れている(偏平足傾向)場合は、インソールやヒールパッドでサポートするのも有効だと言われています。
「痛みが続く場合」は専門家に相談を
セルフケアを続けても痛みが引かない場合や、歩行時にも強い痛みを感じるときは、早めに整形外科や接骨院での触診や検査を受けることが大切です。
無理をせず、適切なタイミングでプロに相談することが、早期改善への第一歩につながるとも言われています。
#シーバー病セルフケア
#かかと痛み対策
#アイシングの方法
#ストレッチ習慣
#専門家に相談を
専門家のアドバイス:整形外科での評価と対応

シーバー病の診断には「触診」が基本
小学生が「かかとが痛い」と訴えた場合、整形外科で行われるのはまず**触診(しょくしん)**です。シーバー病(踵骨骨端症)はレントゲン画像で明確に写らないことがあるため、医師が直接かかとを押して痛みの有無や部位を確認し、症状の出方や運動歴を合わせて診断することが一般的だと言われています。
必要に応じて行う検査と評価
場合によっては、成長期特有の骨の変化を確認するためにレントゲン検査を行うこともあります。ただし、レントゲンで異常がなくても、シーバー病が疑われる場合には症状と経過観察をもとに診断が行われるケースが多いようです。
最近では、超音波エコーによる踵骨周辺の炎症反応を見る検査も用いられていると言われています【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sieberdisease-healquickly/】。
治療より「負担を減らす保存療法」が中心
シーバー病は成長とともに自然に症状が改善することが多いため、特別な治療よりも**保存療法(負担軽減)**が基本とされています。
具体的には、インソールやヒールパッドを使用して踵への負担を和らげる対策や、運動量を調整するアドバイスが行われます。
また、痛みが強い場合には一時的に運動を休止したり、必要に応じて松葉杖を使ってかかとへの荷重を避けることもあります。
いずれにしても、自己判断で「大丈夫だろう」と無理をするのではなく、専門家の評価を受けた上で適切なケアを受けることが重要とされています。
#シーバー病診断方法
#整形外科での検査
#触診の大切さ
#保存療法が基本
#専門家のアドバイスを聞こう
再発予防と普段からできる対策

運動量と休息バランスを見直そう
シーバー病を再発させないためには、運動と休息のバランスがとても大切です。痛みが落ち着いても無理に練習量を戻すのではなく、徐々に運動量を増やしていくことがポイントとされています。特にジャンプやダッシュを伴うスポーツでは、週に1〜2日はしっかりとした休養日を作ることが、かかとへの負担軽減につながるとも言われています。
アキレス腱やふくらはぎの柔軟性アップがカギ
ふくらはぎやアキレス腱が硬くなると、踵の骨に余計な負担がかかりやすくなります。そのため、ふくらはぎのストレッチや足裏のマッサージを日常的に取り入れることが再発防止には有効です。また、タオルギャザーなどの足指トレーニングも、足裏の筋力アップに効果があると言われています。
靴選びやインソールの工夫も重要
普段履く靴にも注意が必要です。かかとがしっかりとホールドされる靴を選び、必要に応じてヒールパッドやアーチサポートインソールを取り入れることで、足にかかる衝撃を和らげることができます。
特に偏平足傾向のお子さんには、専門家に相談して適切なインソールを選ぶのもおすすめです。
違和感が出たら無理せず早めに対処
「少し痛むけど大丈夫」と無理をしてしまうと、再発や悪化のリスクが高まると言われています。違和感や疲労感を感じた段階で休息を取ることが、結果的に早く競技に復帰する近道になる場合もあります。
#シーバー病再発予防
#運動と休息のバランス
#ふくらはぎストレッチ
#靴とインソール対策
#早期対応が重要