制度の背景と改正の流れ

平成30年度介護報酬改定で広がった鍼灸師の活躍の場
平成30年度の介護報酬改定では、機能訓練指導員の対象資格に新たに鍼灸師が加わったと言われています(引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/)。
それまで機能訓練指導員は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが中心でしたが、慢性的な人材不足や高齢者の多様なニーズに対応するため、制度が見直されたとされています。特に、東洋医学の視点を持つ鍼灸師が、生活機能の維持・向上を目的とした機能訓練にも貢献できる点が評価された背景があるとされています(引用元:https://relax-job.com/more-health/4043)。
人材不足対策と多職種連携の強化
改定の背景には、介護施設におけるリハビリ人材の不足がありました。高齢化の進行に伴い、日常生活動作(ADL)の維持や改善を目的とした機能訓練を行う専門職の確保が急務とされていました。その中で、鍼灸師は筋肉や関節の可動域、血行促進などに関する専門知識を活かし、理学療法士や作業療法士と連携しながら利用者の生活機能を支えることが期待されたといわれています(引用元:https://karterrace.seirin.jp/blog/8426/)。
鍼灸師の専門性と機能訓練への適合性
鍼灸師は解剖学や東洋医学に基づくアプローチにより、痛みの緩和や筋肉の緊張緩和を図れるとされています。これらの施術は、利用者が日常生活で動きやすくなる環境づくりにもつながると考えられています。制度改正により、このような鍼灸師の専門性が介護現場でも活かせるようになり、多様な視点からの機能訓練が可能になったといわれています。
#機能訓練指導員 #鍼灸師の資格活用 #介護報酬改定 #人材不足対策 #多職種連携
鍼灸師が機能訓練指導員になるための要件

6ヶ月以上の実務経験が必要とされる背景
鍼灸師が機能訓練指導員として認められるには、特定の条件を満たす必要があると言われています。その中でも重要なのが、他職種の機能訓練指導員(例:理学療法士・作業療法士など)が在籍する施設で、6ヶ月以上の実務経験を積むことです(引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/)。
この条件は、鍼灸師が介護現場における機能訓練の進め方や利用者との関わり方を、実際の現場で学びながら身につけることを目的としていると言われています。制度上、一定期間の経験を通して、多職種との連携や業務フローを理解することが重視されているようです。
実務経験証明書の取得プロセス
6ヶ月以上の実務経験を積んだ後は、その経験を証明するために**「実務経験証明書」**を発行してもらう必要があります。この証明書は勤務先の施設が発行し、勤務期間や担当業務の内容が記載されます(引用元:https://relax-job.com/more-health/4043)。
発行の際には、事前に施設管理者や上司に依頼し、必要な書式や提出先を確認しておくことが望ましいとされています。特に、勤務内容や期間に誤りがあると資格申請に支障が出る可能性があるため、内容の確認を丁寧に行うことが推奨されています(引用元:https://karterrace.seirin.jp/blog/8426/)。
要件を満たすことで広がるキャリアの選択肢
この要件をクリアすると、デイサービスや特別養護老人ホームなど、幅広い介護施設で機能訓練指導員として働く道が開けると言われています。鍼灸師としての知識や施術スキルを活かしつつ、介護現場での生活機能向上に携わることで、利用者の生活の質を支えるやりがいを感じられる可能性があるとされています。
#鍼灸師 #機能訓練指導員 #実務経験証明書 #介護施設での経験 #多職種連携
仕事内容の違い|医療現場と介護現場での鍼灸師の役割
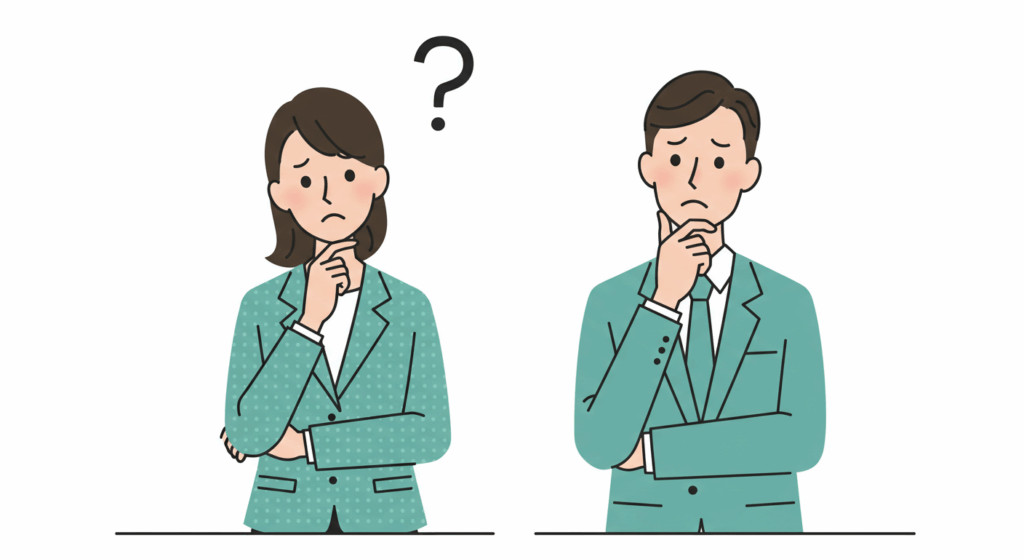
鍼灸院での業務は「症状の改善」に焦点
鍼灸院で働く鍼灸師は、主に来院者の痛みや不調に対して、個別の症状に合わせた施術を行うといわれています(引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/)。
東洋医学の理論や経絡、ツボを用い、肩こり・腰痛・冷えといった体の不調を和らげることが中心で、施術時間も1対1でじっくり行われることが多いようです。施術の目的は、症状の軽減と再発予防、生活の質を高めるサポートとされています。
また、来院者とのコミュニケーションも重要で、生活習慣や体調の変化を確認しながら施術内容を調整する柔軟性が求められるといわれています。
介護施設での業務は「生活機能維持・向上」が目的
一方、介護施設で機能訓練指導員として働く場合、目的は生活機能の維持や向上にあります(引用元:https://relax-job.com/more-health/4043)。
例えば、歩行訓練や関節可動域訓練、筋力トレーニング、バランス練習など、日常生活動作(ADL)の維持を目指すプログラムが中心です。ここでは、痛みの軽減だけでなく、「転倒予防」や「自立した生活の継続」が重視される傾向があります。
施術というよりも、「集団体操」や「日課としての運動支援」など、複数人を対象にした活動が多く、チームで利用者を支える体制になっているのが特徴です(引用元:https://karterrace.seirin.jp/blog/8426/)。
役割の違いがもたらすやりがいの変化
医療現場では施術を通じて直接的な症状の改善を目指すやりがいがあり、介護現場では日々の生活に寄り添いながら長期的なサポートを行う達成感が得られると言われています。それぞれの現場で求められるスキルや視点が異なるため、自分がどの環境で働きたいかを見極めることが重要だと考えられます。
#鍼灸師 #機能訓練指導員 #医療現場と介護現場の違い #生活機能維持 #施術と訓練の役割分担
鍼灸師が担える強みとやりがい

解剖学と東洋医学を融合した痛みケア
鍼灸師は、解剖学的な知識と東洋医学の理論を組み合わせたアプローチで、痛みや筋緊張の緩和を図ることができると言われています(引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/)。
筋肉や関節、神経の構造を理解しつつ、ツボ刺激や経絡理論を活用することで、血行促進や可動域の改善が期待されるとされます。この特性は、介護現場においても役立ち、利用者が日常生活動作(ADL)をよりスムーズに行えるよう支える手段になると考えられています。
ADL改善につながるサポート
介護施設での機能訓練では、利用者が「自分で立ち上がる」「歩く」「食事をとる」などの生活動作を維持・向上できることが大切だとされています(引用元:https://relax-job.com/more-health/4043)。
鍼灸師の施術は、関節の動きや筋肉の柔軟性に働きかけることで、日常動作を行いやすくするサポートになり得るとされます。痛みが軽減されることで運動意欲が高まり、結果的に生活の質(QOL)向上につながる可能性があると言われています。
利用者の自立支援によるやりがい
鍼灸師が介護現場で感じるやりがいのひとつは、利用者の「できること」が増えていく瞬間に立ち会えることです(引用元:https://karterrace.seirin.jp/blog/8426/)。
例えば、歩行器を使って数歩しか進めなかった方が、施術や訓練の積み重ねによって自力で歩ける距離が延びたとき、本人だけでなく家族やスタッフも喜びを共有できます。こうした成果は、鍼灸師としての専門性を活かしながら、生活の現場に密着して働くからこそ味わえる達成感だとされています。
#鍼灸師 #機能訓練指導員 #ADL改善 #自立支援 #介護現場のやりがい
キャリアパスと職場の選び方

働ける主な施設の種類
鍼灸師が機能訓練指導員として活躍できる場は幅広く、代表的なのはデイサービス(通所介護)、特別養護老人ホーム(特養)、ショートステイ、介護老人保健施設などがあると言われています(引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/)。
デイサービスでは日中の時間帯に利用者が集まり、個別または集団での機能訓練を実施するケースが多く、比較的生活リズムが安定しやすい職場とされています。特養やショートステイでは、24時間体制で生活を支える中で機能訓練を行うため、介護スタッフとの連携力が特に求められるようです。
職場環境による業務スタイルの違い
通所型の施設では、利用者が自宅で暮らしながら定期的に通ってくるため、家庭での生活動作を意識した訓練が重視される傾向があります(引用元:https://relax-job.com/more-health/4043)。一方、入所型施設では、長期的な生活支援の中で機能維持・向上を目指すため、日常生活に密着したプログラム作りが必要とされます。施設によって利用者の介護度や健康状態が異なるため、求められるスキルやアプローチ方法も変わってくるといわれています。
キャリアパスを考える視点
キャリア形成の面では、介護現場での経験を積んだ後、施設管理者やリハビリ部門の責任者としての道もあります。また、複数の施設での勤務経験を活かし、研修講師や教育担当として活動するケースもあると言われています(引用元:https://karterrace.seirin.jp/blog/8426/)。
自分の得意分野や働きたい時間帯、職場の規模や理念などを踏まえて選ぶことで、長く続けやすいキャリアを築ける可能性が高まります。
#鍼灸師 #機能訓練指導員 #介護施設の種類 #職場選びのポイント #キャリアパス









