肘を押すと痛いのはなぜ?考えられる主な原因
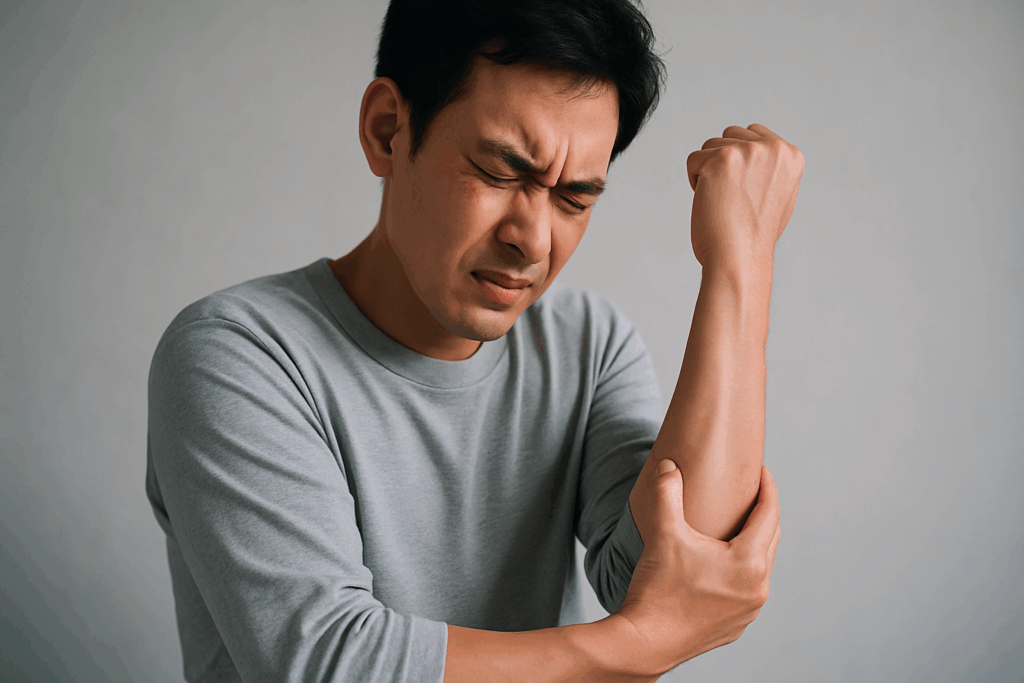
ぶつけた覚えがなくても痛むのはなぜ?
「肘をどこかにぶつけた覚えがないのに、押すとズキッと痛む…」そんな経験はありませんか?実はこのようなケース、意外と多いようです。外傷がなくても痛みが現れる背景には、使いすぎによる炎症や姿勢のクセなど、目に見えない負担が隠れていることがあると言われています。
たとえば、デスクワークや家事、スポーツなどで肘に無意識のうちに繰り返し力が加わると、関節や筋肉、腱などの組織がダメージを受けやすくなるようです。特に痛みが「押したときだけ」出る場合、慢性的な炎症の初期段階であることも考えられるとされています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。
また、加齢による関節周辺の変化や、ホルモンバランスの影響が関係しているケースもあるそうです。いずれにしても、強い痛みでなくても、体が発しているサインとして軽く見ないことが大切です。
肘周辺の筋肉・腱・神経のトラブル
押すと痛む原因として代表的なのが、「テニス肘(外側上顆炎)」や「ゴルフ肘(内側上顆炎)」です。これらはそれぞれ肘の外側・内側の腱に炎症が起こるもので、手首や指を使いすぎることで引き起こされると考えられています。
また、神経が関係するケースもあります。たとえば「肘部管症候群」と呼ばれる神経障害では、肘の内側を押すとビリッとした痛みやしびれを感じることがあると言われています(引用元:https://www.kawamura-seikei.jp/column/gorufuhiji/)。
さらに、「滑液包炎」や「関節内の炎症」が関係している場合もあり、肘の曲げ伸ばしで痛みが強くなる、腫れや熱感をともなう場合は早めの対応が望ましいとされています。
セルフチェックで確認したいポイント
まず、肘のどの部分を押したときに痛みが出るのかを確認してみましょう。外側・内側・真ん中のどこに痛みを感じるかで、おおまかな原因が見えてくる場合もあります。
次に、日常動作で痛みが出る場面を思い返してみてください。たとえば「物をつかんで持ち上げたとき」「ドアノブを回したとき」などに痛みが強くなるなら、テニス肘の可能性が示唆されることがあります(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tennis_elbow.html)。
また、じっとしていてもジンジンするような感覚がある場合や、しびれをともなう場合は、神経の圧迫などが考えられるそうです。このようなときは無理に動かしたり自己判断でマッサージをするよりも、早めに整形外科などで専門的な評価を受けることが勧められています。
#肘の痛み #テニス肘 #ゴルフ肘 #神経トラブル #セルフチェック
症状別|押したときの痛みで疑われる疾患
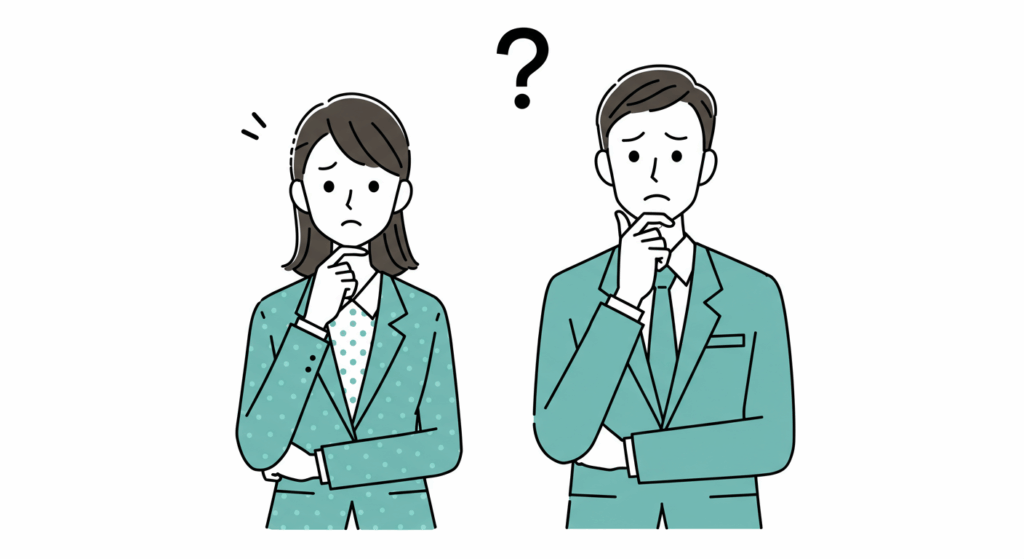
内側上顆炎(ゴルフ肘)の特徴
肘の内側を押したときに痛みを感じる場合、「内側上顆炎(ないそくじょうかえん)」、いわゆるゴルフ肘が関係していることがあると言われています。名前に“ゴルフ”とついていますが、実際にはゴルフ経験がない人にも見られるようです。
特に、手首を内側にひねる動作や、物を握る・持ち上げるときに痛みを感じることが多く、日常生活の中でも負担がかかりやすい部位とされています。デスクワークや家事などでも繰り返し肘の内側の腱が引っ張られることで、炎症が起こりやすくなると考えられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。
初期は押すとズーンとした痛みが出る程度でも、使い続けると鋭い痛みに変化するケースもあるそうです。
外側上顆炎(テニス肘)のサイン
一方で、肘の外側を押すと痛い場合には、「外側上顆炎(がいそくじょうかえん)」、いわゆるテニス肘の可能性が示唆されることがあります。こちらもテニスに限らず、パソコン作業や重い荷物を持つ動作などで発症することがあるようです。
特に、手首を反らす、ドアノブを回す、フライパンを持つなどの動作で痛みが強くなる傾向があるとされています。押すと痛むポイントが肘の外側に集中しているのが特徴です。
このような痛みは、腱の微細な損傷や炎症によって引き起こされるとされており、繰り返すことで慢性化することもあるそうです(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tennis_elbow.html)。
肘部管症候群や滑液包炎の可能性
肘の内側を押すと「ビリッ」と電気が走るような痛みや、指先のしびれがある場合、「肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)」が関係しているケースもあると言われています。この症状は、肘の内側を通る尺骨神経が圧迫されることで起こるそうです。
また、肘の周辺にぷくっとした腫れや熱っぽさがある場合は、「滑液包炎(かつえきほうえん)」のような炎症性疾患が疑われることがあります。これは肘のクッションのような役割をする滑液包に炎症が起きた状態とされていて、長時間肘をつく習慣などがきっかけになることもあるようです(引用元:https://www.kawamura-seikei.jp/column/namida/)。
いずれの症状も、「押したときの痛み」と合わせて、動かしたときの違和感や神経症状の有無などもチェックすることが、対策を考える上で参考になるとされています。
#ゴルフ肘 #テニス肘 #肘の痛み #神経圧迫 #滑液包炎
肘の痛みを感じたときにやってはいけないこと
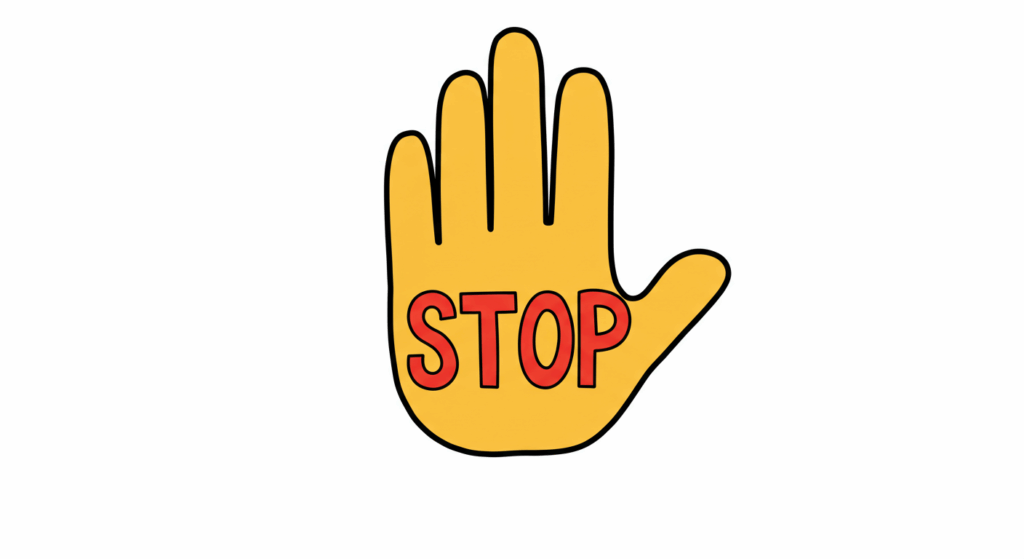
自己判断でのマッサージやストレッチのリスク
肘が痛いとき、「軽い痛みなら、マッサージやストレッチでどうにかなるかも」と考えたことはありませんか?
実際、痛みが気になると、つい揉んでみたり、伸ばしてほぐそうとしたりする方が多いようです。
しかしこのような自己流の対応が、かえって症状を悪化させるケースもあると言われています。とくにテニス肘やゴルフ肘などの炎症性疾患では、負荷がかかった腱や筋肉にさらに刺激を加えることで、炎症が強くなる可能性があると考えられているようです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。
また、神経に関係する症状(例:肘部管症候群)の場合、誤った角度でのストレッチや圧迫は、しびれや痛みを助長することがあるとされています。
一見ラクになるように感じても、その場しのぎの対処で根本的な改善にはつながらないことが多いようです。
自己判断がすべてNGというわけではありませんが、原因がはっきりしない状態でのセルフケアは注意が必要です。痛みが続く、広がる、増すといった変化があれば、無理せず医療機関で検査を受けることが望ましいとされています。
放置することで悪化するケースも
「そのうち良くなるだろう」と様子を見続けるのも、実は注意が必要な行動のひとつです。
特に、押したときの痛みが数日~数週間にわたって続いている場合は、何らかの炎症や組織の損傷が関係していることがあると言われています。
たとえば、軽度の上顆炎であっても、放置している間に筋肉や腱への負担が蓄積すると、日常生活の動作に支障が出るほどの痛みに変化することもあるようです。加えて、滑液包炎のような腫れを伴う症状では、放置によって炎症が拡大するリスクも指摘されています(引用元:https://www.kawamura-seikei.jp/column/namida/)。
症状をそのままにしておくことで、結果的に回復に時間がかかる場合もあります。
「たいしたことない」と軽く見てしまう前に、一度体のサインに目を向けることが、自分自身を守るための第一歩になるかもしれません。
#肘の痛み対策 #自己判断NG #マッサージの注意点 #ストレッチのリスク #放置は悪化のもと
自宅でできる対処法と日常生活の工夫

冷やす・安静にする・サポーターの使用
肘を押すと痛いとき、自宅でできる対処としてまず試してほしいのが「冷却」と「安静」です。特に、痛みが出始めた直後や、熱っぽさ・腫れを感じる場合は、保冷剤や氷まくらをタオルに包んで10〜15分ほど冷やすことが推奨されていると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。
冷やすことで炎症の広がりを抑えることが期待されている一方、長時間冷やし続けると血行が悪くなるリスクがあるため、冷却は適度にを心がけましょう。
また、日常動作での負担を軽くするために、サポーターの使用も一つの手段として考えられています。肘関節にかかる負荷を分散させる効果があるとされており、特にテニス肘やゴルフ肘のような症状には利用されることが多いようです。ただし、サポーターをつけたまま無理な動作を繰り返すと意味が薄れるため、「使いながら休ませる」という意識も大切です。
肘の痛みが強いときには、なるべく片手で無理な動作を避け、負担のかかる作業は一時的に見直すことがすすめられています。
痛みが軽減した後のストレッチと再発防止策
痛みが落ち着いてきたら、再発を防ぐためのケアも少しずつ取り入れていきましょう。ただし、急に筋トレやストレッチを始めると逆に炎症がぶり返すこともあるため、タイミングと内容には注意が必要です。
たとえば、手首や前腕の筋肉をゆっくり伸ばすようなストレッチは、肘への負担軽減にもつながると言われています。無理に強く伸ばすのではなく、「心地よい範囲」で行うことがポイントです。
さらに、普段の姿勢や手の使い方を見直すことも大切とされています。パソコン作業が多い方は、キーボードやマウスの高さを調整する、家事で重い鍋を持つときは両手で支える、など日常のちょっとした動きが予防につながることもあるそうです(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tennis_elbow.html)。
痛みの再発を防ぐためには、**「休ませる」「整える」「負荷を減らす」**という3つの視点を意識することがポイントになりそうです。
#肘の痛み対処法 #冷却と安静 #サポーター活用 #再発防止ストレッチ #日常の動作見直し
医療機関を受診すべきサインと診療科の選び方

痛みが続く、しびれや腫れがある場合は?
肘を押すと痛い症状が「数日以上続いている」「だんだん強くなってきた」「夜間にも痛みが出る」といった場合、セルフケアだけでは難しいケースがあると言われています。特に、しびれや腫れをともなう場合は、神経や関節内部のトラブルが関係している可能性もあるようです。
また、日常生活に支障をきたすような痛み(例えばペットボトルのフタが開けづらい、ドアノブを回すと激痛が走るなど)があるときは、なるべく早めの検査がすすめられているようです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。
症状の程度にかかわらず、「これまでと何か違うな」「ちょっと変だな」と感じた時点で一度専門の医師に相談しておくことで、重症化のリスクを減らせると考えられています。
整形外科・リハビリ科・神経内科などの目安
では、肘の痛みがあるとき、どの診療科に行けばよいのでしょうか?
まず多くのケースで最初に相談されるのが整形外科です。関節・骨・筋肉・腱など、運動器のトラブルに広く対応しているため、テニス肘やゴルフ肘、滑液包炎などの可能性がある場合は整形外科が一般的な入口とされています。
次に、**リハビリテーション科(リハビリ科)**も選択肢のひとつです。医師の指導のもと、物理療法や運動療法を通じて、症状の緩和や再発予防を図る方も多いようです。
また、痛みだけでなく「しびれ」「感覚の異常」が気になる場合には、神経内科への来院も視野に入ることがあります。肘部管症候群など、神経由来の症状が疑われるケースでは、神経の伝導検査が行われることもあるそうです(引用元:https://www.kawamura-seikei.jp/column/gorufuhiji/)。
ただし、最初からどこに行くか迷った場合には、整形外科を起点に紹介を受けるという流れも一般的です。
診察時に伝えるべきポイントと診断の流れ
医療機関での触診では、限られた時間の中で状況を把握してもらうために、「痛みの出始めた時期」「どのような動作で痛むか」「腫れや熱っぽさがあるか」などを整理しておくとスムーズです。
また、「ぶつけた記憶がない」「徐々に痛くなってきた」「物を持つと痛い」といった自覚症状を具体的に伝えることで、炎症なのか神経の圧迫なのかといった見立ての助けになると言われています。
触診では、必要に応じてレントゲン検査、超音波検査、神経の伝導テストなどが行われることがあります。こうした検査は、それぞれの疾患を絞り込むために活用されているようです(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/tennis_elbow.html)。
不安な点や気になることがあれば遠慮せずに質問することも、納得して対策を進めるための一歩となります。
#肘の痛みと医療機関 #整形外科に相談 #しびれや腫れのサイン #診察時の伝え方 #診療科の選び方









