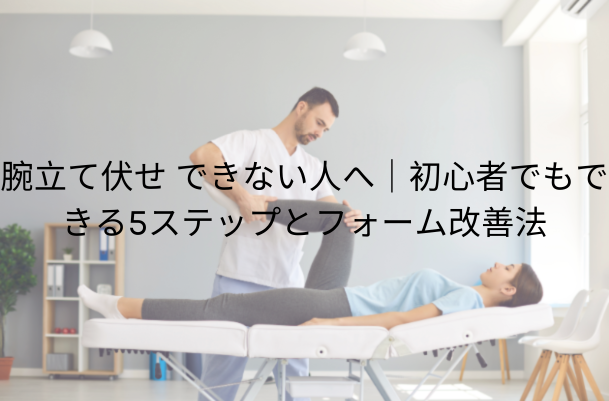なぜ腕立て伏せが“できない”の?原因を知ろう

腕立て伏せって、いざやろうとすると「え、全然できない…」ってなること、ありませんか?実はそれ、筋力不足だけが理由じゃないと言われています。例えば大胸筋の筋力が足りないと、カラダを下ろして持ち上げる段階で力が出づらいスティッキングポイントに引っかかることがあるそうです(引用元:melos.media)。さらに、「上腕三頭筋」の筋力が弱いと、胸は平気でも腕がお先にバテちゃうタイプが多いようです(引用元:melos.media)。
あとは体幹の弱さ。腕立て伏せは腕とつま先で体重の約6割を支えるから、バランス力がないとフォームが崩れて、そのへんが「できない」感につながると言われています(引用元:katagirijuku.jp、hybrid-tsutsumi.jp)。
しかも、体重が重いとその分支える負荷が増えて、筋力が追いつかないこともあるそうで、これは初心者あるあるなのかな、と思います(引用元:pushup-thehero.com、katagirijuku.jp)。
結局、「できない」現象はいくつもの要素が絡み合っていて、個人差も大きいのが実状な気がします。ただ、ここを理解するだけで「自分だけじゃないし、対策もちゃんとあるんだ」と安心できそうですよね。
#筋力不足 #体幹弱い #体重の影響 #フォーム崩れ #初心者あるある
壁で予備練習!ウォールプッシュのメリットとやり方

「地面じゃ無理!」って人がまず試したいのが、壁腕立て伏せ。これ、腕立て伏せの基本姿勢を軽い負荷で体に覚えさせるにはぴったりなんです。角度がゆるいから、腰や肩へのダメージを避けつつフォームを学べると言われています(引用元:rehasaku.net)。
やり方は簡単で、壁に手をついて体をまっすぐに保ちながら、胸が壁に近づくようにゆっくり曲げるだけ。力を入れて戻すときに息を吐くのがコツ、と教わることもあるみたいです(引用元:note.com、rehasaku.net)。
「でも、これほんとに効くの?」と思うかもしれませんが、台や壁などで負荷を調整すると、体幹や腕への刺激もありつつ、安全に練習できると言われています(引用元:note.com)。
まさに、地面の腕立て伏せへの“はしご段階”としてぴったり。軽い負荷から始めたい人にはおすすめのステップだと思います。
#軽負荷練習 #フォーム習得 #壁腕立て #安心ステップ #基礎訓練
膝つき腕立て伏せ:初心者向けステップ

「壁はちょっとできるようになってきたけど、まだ地面は無理…」ってときに次におすすめなのが、膝つき腕立て伏せ。膝をつくことで体重の一部を減らしつつ、地面近くでトライできるから、腕立て伏せへの橋渡しに最適と言われています(引用元:melos.media)。
やり方としては、膝から頭までを一直線に保ち、胸が床につく少し手前くらいまでゆっくり下げて、また体を押し上げる感じ。10回×3セットがよく目安にされてます(引用元:melos.media)。フォームでは「腰が反らないように」「体をまっすぐキープ」「目線は斜め前方」という点がよくアドバイスされていて、やってみると意外と体幹に効いて「やってよかった」と思える方も多いようです(引用元:melos.media)。
初心者さん同士で「膝つきで10回できた!」っていう報告をし合うことすらあるくらいです(笑)。
#膝つき練習 #負荷軽減 #体幹意識 #10回3セット #橋渡しステップ
正しいフォームを身につけて効率よく鍛える

膝つきまでできるようになってきたら、次はフォーム固めがカギ。正しい腕立て伏せでは、頭からかかとまで一直線が基本で、お尻が上がり過ぎたり、腰が反ったりしていると、腰や肩に余計な負担がかかると言われています(引用元:co-medical.mynavi.jp、katagirijuku.jp)。
手の位置は肩幅より少し広めがいいとされ、肘が外側にダラーンと開くと効かせたい筋肉に刺激が入りづらいとも言われています(引用元:rehasaku.net、katagirijuku.jp)。また、体幹にも気を配って「お尻をキュッ」「お腹に軽く力を入れる」イメージでフォームを安定させると効果アップとも言われています(引用元:hybrid-tsutsumi.jp)。
こうしたフォームが習慣になると、腕立て伏せの効率がグッと上がって「疲れづらくなったかも?」という変化を感じやすくなる気がします。
#一直線姿勢 #腰反らない #手幅調整 #お腹に力 #効率アップ
ステップアップのコツと継続の秘訣
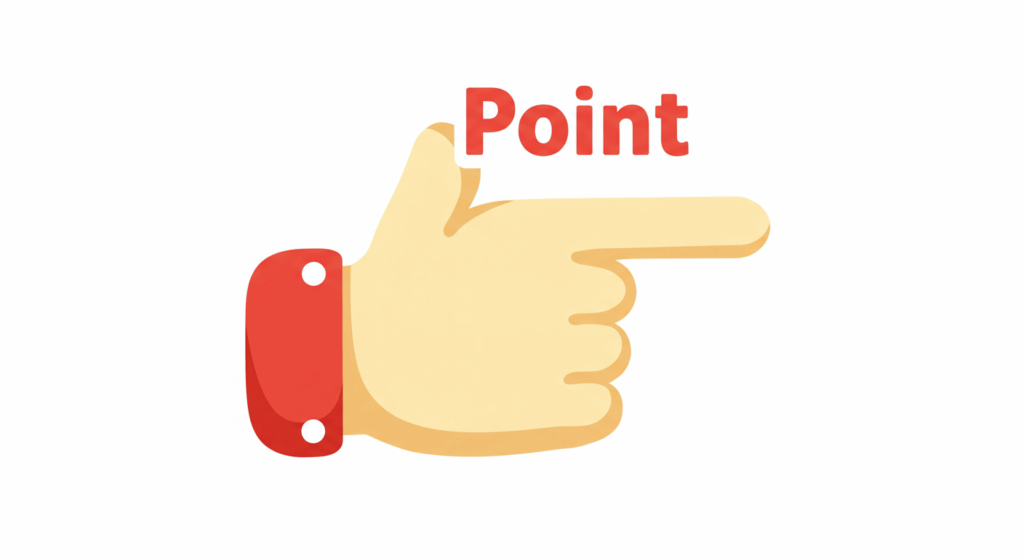
「ステップをひとつクリアしたら、次どうする?」という話になると、やっぱり継続のコツが知りたいですよね。まずは回数より“質重視”で、5〜10回を丁寧にこなすのが基本と言われています(引用元:rehasaku.net)。
「毎日やらないと…」と焦りが出ることもあるけど、筋肉を休ませる時間(2〜3日に1回ペース)を設けたほうが効果的とも言われているようです(引用元:rehasaku.net)。
だんだん負荷を上げたい人には、インクラインプッシュアップ(台などの高いところで)などのバリエーションも紹介されていて、飽きずに楽しく続ける工夫がされている記事もあります(引用元:kinntore-college.com、melos.media)。
「少しずつできる回数が増えてきた」「なんだか体が軽くなった気がする」といった小さな実感を積み重ねていくのが、継続の最大の秘訣かもしれません。
#質重視 #休息も大事 #回数増やす工夫 #バリエーション追加 #継続の楽しさ