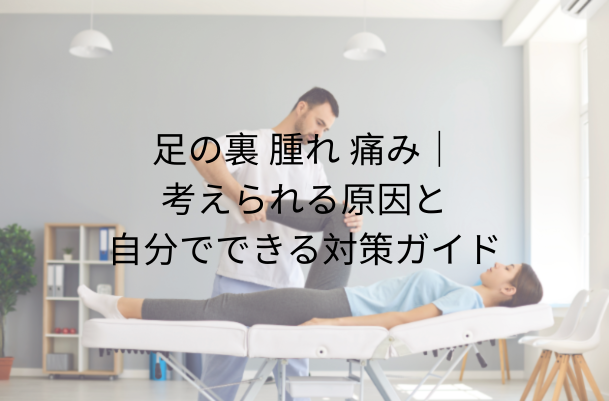足の裏の腫れ・痛みで知っておきたい代表的な疾患

足底筋膜炎|朝の一歩目がつらい方は要注意
足裏の痛みと聞いて、まず疑われるのが「足底筋膜炎(そくていきんまくえん)」です。かかとの内側から足指の付け根まで広がる足底筋膜という組織に炎症が起こることで、歩き始めや長時間の立ち仕事の後に強く痛む傾向があると言われています。特に朝起きてすぐの一歩目が痛いと感じる場合、この疾患が疑われることが多いようです【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sole-of-foot-pain/】。
モートン病|足指のつけ根がしびれる・痛む
ヒールや窮屈な靴をよく履く方に多いのが「モートン病」です。これは第3・第4趾の中足骨の間で神経が圧迫され、しびれや焼けるような痛みが出るのが特徴とされています。歩行中やつま先立ちで痛みが増すケースもあるようです。
外反母趾・内反小趾|親指・小指の変形が影響するケースも
足のアーチ構造が崩れ、親指(外反母趾)や小指(内反小趾)が内側へ傾くことで、足裏に余計な負担がかかることがあります。その結果、足底に炎症が起き、腫れや痛みにつながるケースも報告されています。
神経や血管のトラブルによるものも
足裏の違和感や腫れが慢性的に続く場合、末梢神経障害や循環器系の疾患が関係していることもあるようです。特に糖尿病の既往がある方は、足の感覚や傷の治りに異常がないか、定期的に確認することがすすめられています。
自己判断せず、専門機関での検査を
「たかが足の痛み」と放っておかず、痛みや腫れが数日以上続く、もしくは悪化する場合は整形外科などでの検査が望ましいと言われています。早期対応が、悪化の予防につながると考えられています。
#足の裏の痛み
#足底筋膜炎
#モートン病
#外反母趾
#セルフケア注意点
痛む場所から原因を判断するチェック法
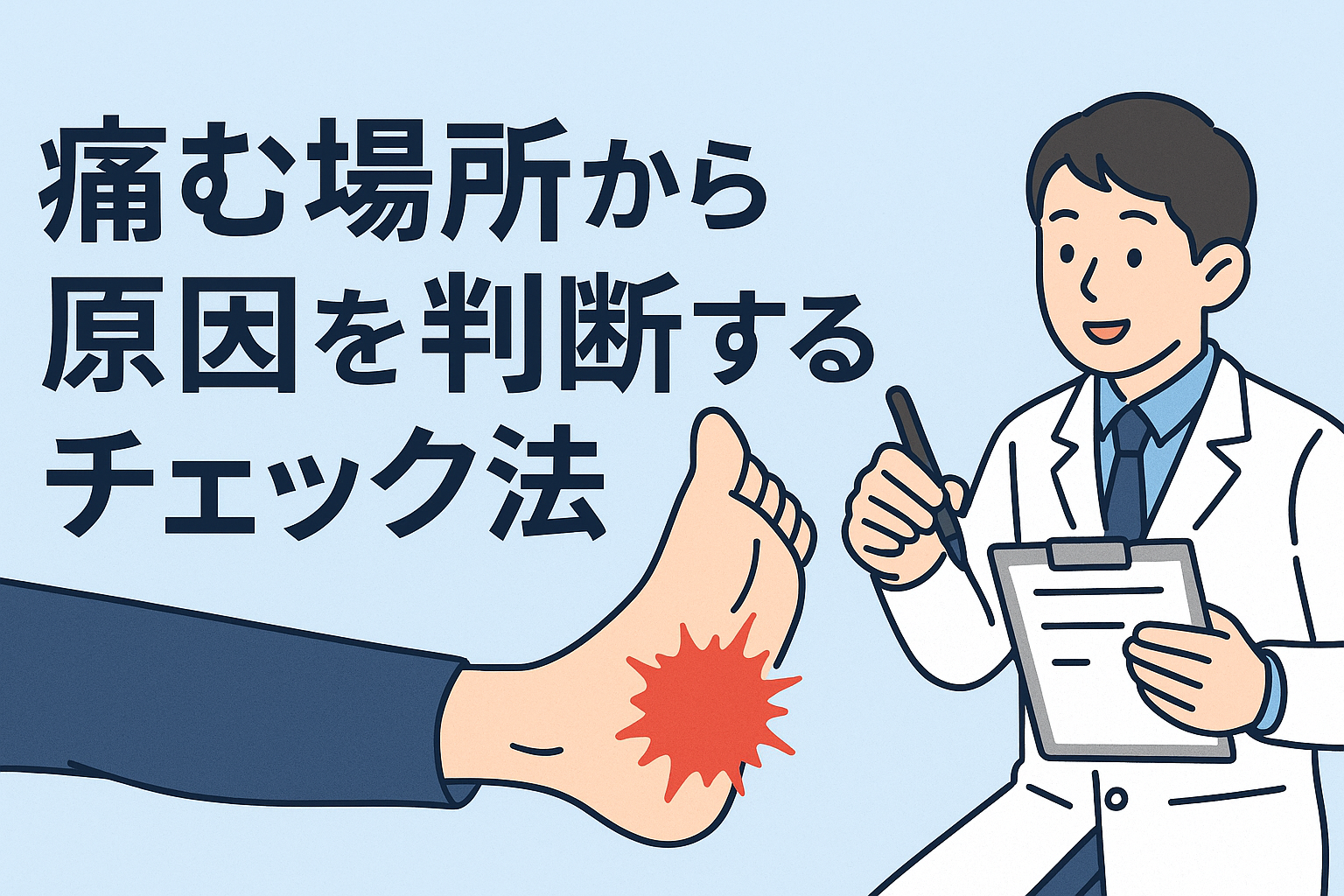
足の裏の「どこが痛いか」を意識してみよう
足の裏が痛いとき、ただ「足裏が痛い」と一括りにしてしまうと、原因の特定が難しくなることがあります。実際には、痛みの出る位置によって考えられる原因が異なるとされています。
たとえば、かかと寄りの内側が痛む場合、足底筋膜炎が関係している可能性があるとされています。一方、足指のつけ根部分にズキズキとした痛みを感じるようであれば、モートン病や中足骨骨頭痛などが関係しているケースもあるようです【引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sole-of-foot-pain/】。
左右差や腫れの有無も判断材料になる
片足だけに痛みや腫れが出る場合は、外傷や局所的な炎症の可能性もあります。逆に、両足にわたって痛みがある、あるいは浮腫(むくみ)が強いという場合は、血行不良や内科的疾患が影響しているとも言われています。
痛みの出るタイミングにも注目
「朝起きた直後に強く痛む」「長時間歩いたあとにジンジンする」など、痛みが出るタイミングも大切な判断材料になります。朝だけ痛む場合は、足底筋膜が夜間に固まり、動き始めにストレスがかかることで痛みを感じることがあるようです。
靴や歩き方のクセが原因になることも
サイズの合っていない靴や、底のすり減った靴を履いていると、特定の部位に負担が集中しやすくなります。また、歩き方のクセ(例えば外側重心や内股歩行)が原因で、足裏の一部に過剰な負荷がかかる場合も考えられるようです。
記録をつけると医療機関での相談にも役立つ
どこが、いつ、どんな風に痛むのか。症状を日記のように記録しておくことで、来院時に医師や専門家が状況を把握しやすくなると言われています。市販の足型チェック表やアプリを活用して、自分でパターンを把握しておくのもおすすめです。
#足の裏の痛み
#セルフチェック
#痛みの場所で原因を考える
#足底筋膜炎の特徴
#歩き方と足の負担
セルフケアで痛みや腫れを軽くする方法

足の裏に腫れや痛みを感じたとき、いきなり病院に行く前に、自宅でできるセルフケアを試してみたいと考える方は多いと思います。もちろん重症の場合は医療機関での検査が必要ですが、軽度なものであればセルフケアによって緩和を目指せることもあると言われています。
冷却と休息を基本に
まず腫れがある場合は、冷やすことで炎症をおさえる効果があるとされています。保冷剤や氷をタオルで包んで、15〜20分程度を目安に患部に当てましょう。冷やしすぎは逆効果となることもあるため、様子を見ながら行うのがポイントです。
また、無理に歩いたり運動を続けると、悪化の原因になるケースもあるといわれています。痛みを感じたら、まずは安静にして体を休める時間を作りましょう。
足裏のストレッチとマッサージ
筋肉や腱が硬くなると、足裏に余計な負担がかかるとも言われています。軽いストレッチやマッサージで血行を促し、筋肉の緊張をゆるめることが、痛みの軽減につながる可能性があります。
たとえば、ゴルフボールや凍らせたペットボトルを足裏で転がすような運動が効果的と紹介されていることもあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/sole-of-foot-pain/)。
靴の見直しも忘れずに
足に合っていない靴は、痛みや腫れの原因になるといわれています。クッション性が不十分だったり、かかとが浮いていたりする靴を履いていると、足底筋膜などに過剰な負担がかかる可能性があります。日常的に履く靴こそ、慎重に選ぶようにしましょう。
痛みが続くときは無理せず相談を
セルフケアを行っても数日経っても痛みや腫れが改善しない場合は、無理をせず整形外科など専門機関への来院を検討することがすすめられています。症状が軽いうちの対応が、長引かせないためのカギになると考えられています。
#足裏の痛み対策
#腫れのセルフケア
#冷却と休息が大切
#ストレッチでケア
#靴の見直しがポイント
症状が続く・悪化したときにすべきこと

我慢しすぎず、変化を見逃さないことが大切
足の裏に腫れや痛みがある場合、数日安静にしても改善しない、あるいはむしろ痛みが増すようなら、「自然に良くなるはず」と思い込まず、一度状況を見直すことが必要だと言われています。とくに、朝起きたときに強い痛みがある・歩行に支障が出る・赤く腫れて熱を持つといった症状は、放っておくと悪化のリスクがあるとも考えられています(引用元:Rehasakuマガジン)。
日々の生活で「なんとなく変だな」と感じた段階で、まずはセルフチェックや生活習慣の見直しを行うのがよいとされます。それでも変化がない、または症状が強くなってきた場合は、速やかに専門機関に相談することが勧められています。
来院の目安と伝えるべきポイント
来院を検討する目安としては、「痛みが1週間以上続く」「圧痛が強くなった」「左右差が明確にある」といったケースが挙げられています。また、医療機関では症状を正しく伝えることが施術のヒントにもなるため、以下のような点をメモしておくとスムーズです。
- 痛みの出たタイミングやきっかけ
- どのような動作で痛みを感じるか
- 痛みの程度や性質(ズキズキ・チクチクなど)
- 日常生活で困っていること(例:歩行・階段)
自分の体の状態を把握しておくことで、医師や施術者にとっても判断材料が増え、適切な検査・施術へつながりやすいと言われています。
#足の裏の痛み対策
#来院の判断基準
#我慢しないケア
#医療相談のすすめ
#歩行に支障があるとき
靴選びや生活習慣で再発を予防しよう

足に合った靴を選ぶことが第一歩
足の裏の痛みや腫れが落ち着いたあとも、「また同じことが起きたらどうしよう」と不安になる方は少なくありません。そんな方にとって、再発予防のための靴選びはとても重要だと言われています。
特に、土踏まずのサポートがしっかりしたインソールや、かかとの安定感がある靴を選ぶことが大切とされます。また、ヒールが高すぎる靴やクッション性のないスニーカーは、足裏に余計な負担がかかることもあるようです。
靴を新調する際は、夕方など足がむくみやすい時間帯に試着し、歩行中に痛みや違和感が出ないか確認しておくのが良いと言われています。見た目よりも「足に合っているか」を基準にすることが再発予防のポイントです。
日常のクセや生活動作も見直してみよう
靴の見直しと合わせて、普段の歩き方や姿勢のクセもチェックしておくとよいでしょう。たとえば、足の外側ばかりに重心がかかっていたり、長時間の立ち仕事で同じ姿勢が続いていたりする場合、それが痛みの一因となることもあるようです。
仕事中や家事の合間に軽く足を回したり、足指を動かす体操を取り入れたりすることで、足裏の負担が分散されるとも考えられています(引用元:Rehasakuマガジン)。また、入浴後のストレッチなど、血行を促す習慣も予防には有効とされています。
「ちょっとした違和感」を見逃さず、足と向き合う時間を日常に少し取り入れることで、再発を防ぎやすくなると考えられています。
#足裏の痛み対策
#靴選びのポイント
#生活習慣の見直し
#足の再発予防
#インソールの活用