法律に則った掲載内容とは?広告規制のポイント

ねえ、チラシ作るときって「何を載せていいの?」って迷うよね。鍼灸チラシの場合、あはき法(正式には「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」)で、載せていい内容が決まっていて、それ以外はNGと言われています。
あはき法で掲載できる項目は?
たとえば、普通に載せていいのはこんな内容です:
- 「施術者の名前・住所」「施術所の名称・電話番号・所在地」「業務の種類(はり・灸など)」などの基本情報はOKです リザービア+6mm-laboratory.com+6karterrace.seirin.jp+6厚生労働省+10リザービア+10株式会社アシスト+10。
- 「施術日や受付時間」「予約制かどうか」「出張施術が可能かどうか」「駐車場の案内」なども、親切さを伝えるうえで問題なく書けるんです mm-laboratory.com+1。
- あと、「健康保険の適用可否」もOK。ただし、医師の同意が必要な場合は、その旨をきちんと明記するのが条件とされています 合同会社クミディアウェブマーケティング+3リザービア+3あきばれ治療院HP作成講座(集客SEOノウハウ)+3。
こういう内容って「利用者が安心して選べるようにする情報」で、客観的にも確認しやすいっていうのがポイントなんだそうです 厚生労働省。
あはき法で掲載しちゃいけない項目は?
では逆に、載せてはいけないのはどんな内容かと言うと……
- 施術者の経歴や学歴、実績、あるいは「当院の実績は〇〇件!」みたいな数字や強調表現はアウトとされています 厚生労働省+4mm-laboratory.com+4karterrace.seirin.jp+4。
- また、「〇〇流の施術」など流派や具体的な施術方法をアピールするのもNG mm-laboratory.com+1。
- もちろん「○○が治る」「完全改善!」など、断定的な表現も禁止です。こういう断定は薬機法や医師法にも抵触しやすいから、載せてはいけないと言われています 接骨院・整骨院・鍼灸院の開業支援なら全国統合医療協会。
#あはき法 #掲載可能事項 #NG表現 #広告規制 #自然な表現
ペルソナ設定で差をつけるチラシ設計

「ねえ、誰に届けたいか考えたこと、ある?」って感じです。チラシ作成で重要なのは、「誰に読んでほしいか」を具体的にイメージすること。これが「ペルソナ設定」と呼ばれていて、整体院のチラシやマーケティングでよく取り上げられています。ターゲットがぶれないから、伝えたいことがブレずに伝わりやすいと言われていますato-co.jp+1。
たとえば、地域に住む高齢者層を狙うなら、「近所のスーパー帰りの70代の女性」とか具体的に想像してみる。そうすると、「足が痛くて外出がしづらい」などのお悩みに寄り添ったフレーズやデザインを考えやすくなるんですよね。また、ポストに届いたチラシを見たとき、「あ、自分のことだ」と思ってもらえるかどうか、その響く精度を高められると言われています株式会社ディプシークリニックマーケティング |。
地域住民や高齢者に刺さる訴求ポイントとは?
じゃあ、具体的にどう訴えるか?例えば高齢者や地域住民へ向けたチラシなら…
- 「安心して通える地元院」として訴求:近隣の安心感や、徒歩・車ですぐ来れる利便性を前面に出す。
- 高齢者に響く言葉選び:例えば「体の不調にやさしく寄り添う」とか、「痛みをなんとかしたい方におすすめ」「まずは気軽に相談だけでも…」など、柔らかい表現にすると自然に受け入れられやすいかも。
- 差別化につながる情報:たとえば「夜も受付」、「駐車場完備」、「訪問施術あり」など、他院にはないポイントを明示するのが重要ですクリニックマーケティング |+3assist-all.co.jp+3big-oasis.com+3〖公式〗RIPICLE(リピクル)電子カルテ・顧客管理・予約管理システム –。
こうした情報を通じて、「あ、これ自分のためのサービスだな」と感じてもらえる工夫をすると、チラシの効果もグッと上がると言われていますidononippon.comクリニックマーケティング |。
#ペルソナ設定 #地域密着 #高齢者向け訴求 #差別化ポイント #読みやすい言葉
一貫性あるデザイン設計で信頼感を高めよう

「ねえ、このチラシ、なんかバラバラに見えない?」って、こういうことよくあるよね。色やフォントが合っていないと、読みにくいし、院の雰囲気も伝わりづらいと言われています(idononippon.com)。だからこそ、デザインに統一感を持たせるのが大切ってわけ。
カラーは、院のイメージに合ったテーマを一貫して使うのが基本。例えば、自然で落ち着いた雰囲気なら緑や茶系、明るくあたたかい印象なら暖色系を基調にするといいと言われています(zenkoku-iryo.com)。これで「この院らしさ」がパッと伝わるようになります。
フォントや写真の使い方で「読みやすさ」と「雰囲気」も伝える
それに、フォントの選び方ひとつでチラシの印象は大きく変わりますよね。清潔感のあるシンプルなフォントを選んで、サイズや太さも工夫することで読みやすさがすごくアップすると言われています(chunichi-sekkotsu.com)。背景とのコントラストも意識しておくと、文字が埋もれずに読みやすくなります(mm-laboratory.com)。
写真を使うときは、施術の様子や院の雰囲気が伝わるものがいいですよね。リアルなシーンを取り入れることで「ここに通いたいな」と思ってもらえる可能性が高まると言われています(chunichi-sekkotsu.com)。でも、ただ載せるだけじゃなくて、色やフォントと調和させることで、自然な一体感が生まれます。
#デザイン統一 #フォント統一 #読みやすさ重視 #写真活用 #院の雰囲気
チラシからWEBへ、自然につながる導線設計

「ねえ、せっかくチラシを手にとってくれたなら、その先もつながればいいと思わない?」って感じです。QRコードをちょっと工夫して載せておくと、読んだ人がスマホですぐ院のホームページやSNSに飛べるようになると言われています 〖チラシ作成専門〗デザイン+印刷のCHIRASAKU(チラサク)+3ビッグオアシス+3株式会社アシスト+3。チラシは“きっかけ”でしかない。だから、そこからオンラインで詳しく知ってもらう導線を自然につくるのが大事なんです 治療院集客集団WAO接骨院・整骨院・鍼灸院の開業支援なら全国統合医療協会。
QRコードと一言コピーでスムーズ誘導
で、具体的にはどうするかというと…
- QRコードは目立つ位置に配置:チラシの右下や中央あたりに大きめに載せて、「スマホでカンタンにアクセス!」みたいな一言を添えるといいと言われています 株式会社リアライズ+9〖チラシ作成専門〗デザイン+印刷のCHIRASAKU(チラサク)+9kuruin+9。
- 導線は絞るのがコツ:ホームページもLINEもSNSも全部載せたくなるけど、それだと分散して反応が薄くなることがあるそうです。最終的に“誘導したい先”は一つにまとめたほうが、効果的と言われています ビッグオアシス。
- SNS限定のキャンペーンもアリ:「このチラシを見た人はインスタフォローで初回施術10%オフ!」と宣言して、QR→SNSの流れをつくると費用対効果が上がるんだそうです ビッグオアシス+3〖チラシ作成専門〗デザイン+印刷のCHIRASAKU(チラサク)+3mm-laboratory.com+3。
#チラシからWEB導線 #QRコード活用 #誘導一括化 #SNSキャンペーン誘導 #自然なつながり
配布戦略と効果測定でチラシの効果を伸ばす
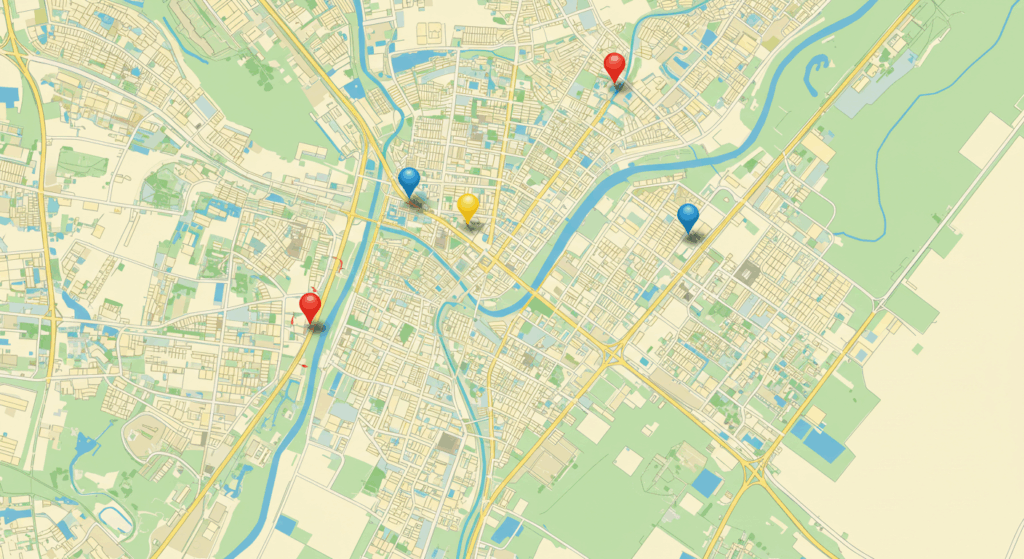
「ねえ、この前のチラシ、どこに配った?」――配布先やタイミングを決めずにばらまくと、反応が薄くなってしまうことがあると言われています(引用元:zenkoku-iryo.com)。だからこそ、配布エリアや時間帯を戦略的に考えることが大切です。さらに、配布後の反応を数字で把握して、次の施策に反映させる流れ、つまりPDCAサイクルを回すことが重要とされています(引用元:big-oasis.com)。
配布エリア・時間帯の最適化と反応率アップの工夫
まずは「どこに配るか」です。院から徒歩圏や車で5分以内の住宅街は、高齢層や地域住民へのアプローチに向いていると言われています。スーパーや商店街の近くなど、人通りの多いエリアも有力候補です(引用元:idononippon.com)。
次に「いつ配るか」。平日昼間は主婦や高齢者、夕方以降は仕事帰りの社会人など、時間帯によって出会える層が変わります。対象に合わせて配布時間を調整すると、目に留まる確率が上がると言われています。
配布後は必ず反応率をチェックします。例えば、チラシ限定の割引や「このQRコードから予約すると○○」などの特典を設定し、反応件数を記録すれば効果測定がしやすくなります。この数字をもとに、「このエリアは反応が良かったから増やそう」「この時間帯は減らそう」と改善策を考えるのがPDCAの“Check”と“Act”の部分です。
#配布戦略 #PDCA活用 #反応率測定 #時間帯最適化 #エリア選定









