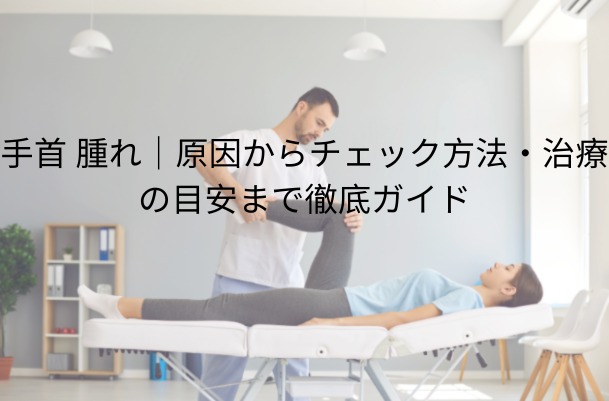手首が腫れる原因とは?—代表的な疾患を一覧で紹介
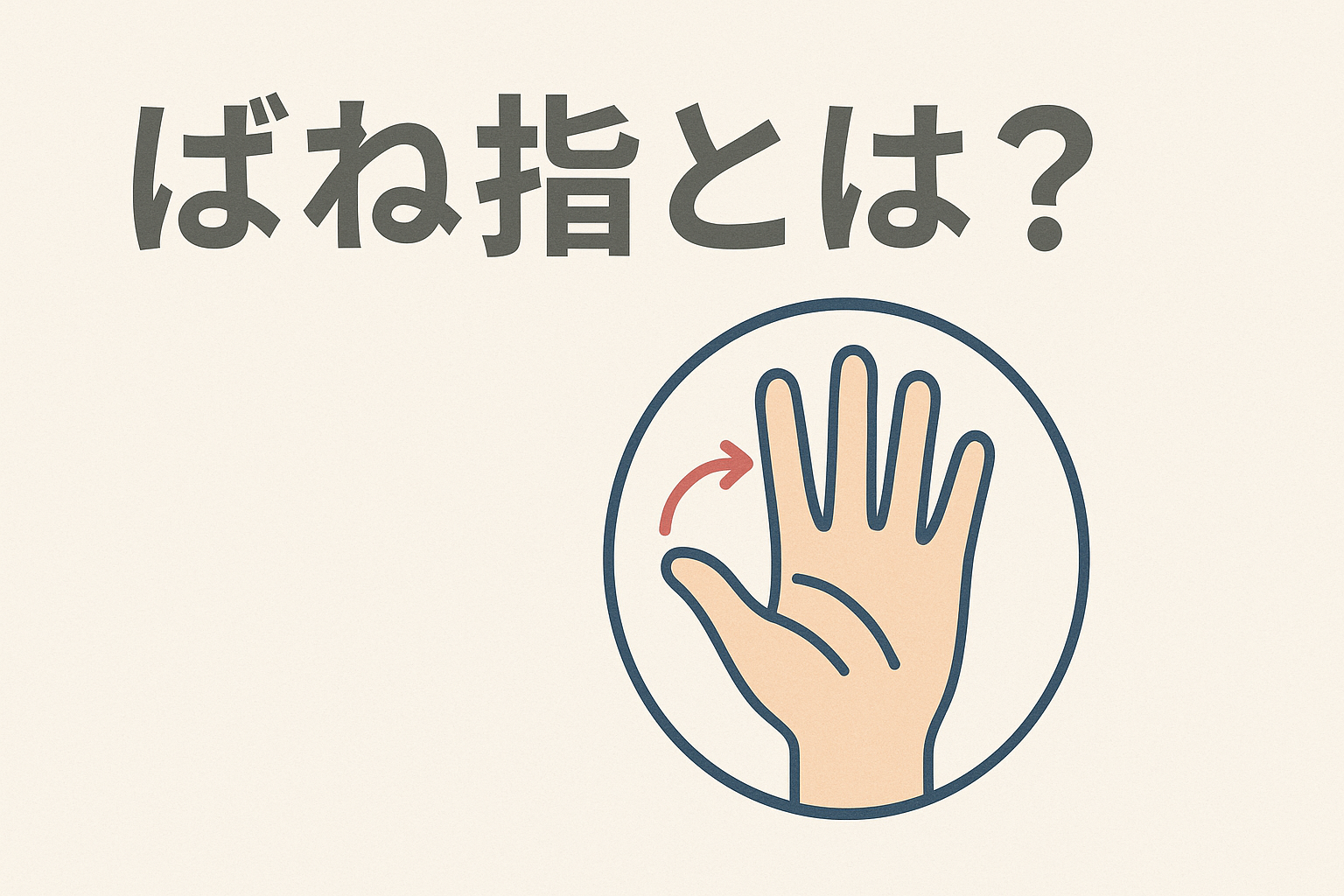
手首の腫れは、日常生活の中で比較的よく見られる症状ですが、その背景にはさまざまな疾患が隠れていることがあると言われています。ここでは、代表的な原因について整理します。
腱鞘炎(ドケルバン病、ばね指)
腱鞘炎は、手首や指の腱を包む腱鞘が炎症を起こして腫れる状態を指すと言われています。特にドケルバン病は、親指側の手首に痛みと腫れが出ることが特徴とされ、ばね指は指の動きが引っかかる感覚と共に腫れを伴うケースがあるそうです。繰り返しの動作や手首の酷使が関与する場合が多いとされています(引用元:mediaid-online.jp、メディカルノート、ドクターズ・ファイル)。
ガングリオン
ガングリオンは、関節や腱の近くにゼリー状の液体がたまってできる良性の腫瘤とされています。手首の背側にできることが多く、腫れが目立つ一方で、痛みがない場合もあると言われています。大きくなったり痛みがある場合は、整形外科での検査が検討されることもあるそうです(引用元:メディカルノート)。
関節リウマチ、乾癬性関節炎、リウマチ性多発筋痛症
これらは自己免疫が関節や筋肉を攻撃することで炎症を起こし、腫れやこわばりが続く疾患とされています。関節リウマチでは、手首を含む複数の関節に左右対称の腫れが見られることがあるそうです。乾癬性関節炎は皮膚症状と関節症状が併発し、リウマチ性多発筋痛症は高齢者に多く、手首以外の部位にも強い炎症が現れるとされています(引用元:ねもと内科クリニック、sato-naika.org)。
骨折(橈骨遠位端骨折など)、キーンベック病
転倒やスポーツなどの外傷で起こる骨折は、手首に強い腫れや痛みをもたらすことがあると言われています。特に橈骨遠位端骨折は中高年女性に多いとされ、骨粗しょう症が背景にあることもあります。キーンベック病は手根骨のひとつである月状骨が壊死する疾患で、進行すると腫れや可動域制限を引き起こすとされています(引用元:mediaid-online.jp、メディカルノート、hand-orth.com)。
その他:成人スティル病、膠原病、悪性リンパ腫、接触皮膚炎など
手首の腫れは、稀に全身性の炎症性疾患や悪性腫瘍、皮膚のアレルギー反応が関係することもあると言われています。成人スティル病や膠原病は全身の関節に炎症を起こし、悪性リンパ腫ではリンパ節や周囲組織の異常によって腫れが出る場合があるそうです。接触皮膚炎では、手首周囲にかぶれや発赤とともに腫れが生じるケースもあります(引用元:Ubie、mediaid-online.jp、メディカルノート)。
#手首腫れ #腱鞘炎 #ガングリオン #関節リウマチ #骨折
自宅でできるチェック方法と見分けポイント

手首の腫れを感じたとき、「これって病院に行ったほうがいいのかな?」と迷う方も多いと言われています。ここでは、医療機関を受診する前に、自宅で確認できるポイントや簡単なチェック方法をご紹介します。
症状の比較:左右差・腫れ具合・熱感・シワの消失
まずは、左右の手首を見比べることが基本とされています。腫れがある側は、反対の手首と比べて太く見えたり、皮膚のシワが薄くなることがあるそうです。また、手首を触ってみて、熱っぽさ(熱感)があるかどうかを確認するのも目安になると言われています。熱感がある場合は炎症や感染の可能性が考えられ、冷たさを感じる場合は血流障害が関与していることもあるそうです。
引用元:ねもと内科クリニック、RAクリニック
フィンケルシュタインテスト(ドケルバン病の簡易確認)
ドケルバン病と呼ばれる腱鞘炎の一種では、特有のテストで症状を確認できることがあると言われています。方法は、親指を他の4本の指で包み込み、そのまま手首を小指側に曲げる動作です。このとき、親指側の手首に強い痛みが走る場合は、腱鞘に炎症がある可能性が指摘されています。ただし、この方法はあくまで簡易的なチェックであり、強く行うと症状を悪化させることもあるため、やりすぎには注意が必要とされています。違和感や痛みが続く場合は、早めに専門家による触診を受けることが望ましいと言われています。
引用元:mediaid-online.jp、RAクリニック
自宅チェックの際の注意点
自宅でのセルフチェックは、あくまで目安として活用することが大切とされています。痛みが強くなるような動作や無理なストレッチは避け、腫れが長引く・悪化する場合は早めに来院が勧められています。特に、外傷後の腫れや、発熱を伴う腫れは感染や骨折の可能性もあるため、放置しないほうが良いとされています。
#手首腫れ #セルフチェック #左右差 #熱感 #フィンケルシュタインテスト
いつ整形外科・内科を受診すべき?受診の目安と注意点
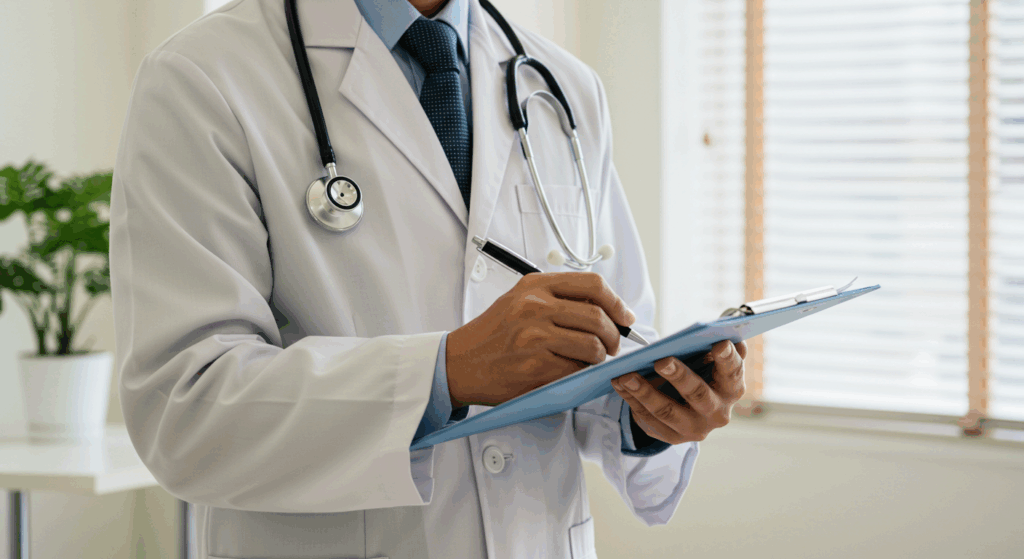
手首の腫れは軽度であれば自然に改善していくこともあると言われていますが、中には重大な疾患が隠れている場合もあるそうです。ここでは、整形外科や内科への来院を検討すべき目安と、その際の注意点について整理します。
急性の痛み・強い腫れ・動かせない場合
突然の激しい痛みや急速に腫れが広がる場合、また手首を動かすことが困難な場合は、骨折や感染症の可能性があると言われています。特に外傷後に痛みと腫れが強く出たときは、橈骨遠位端骨折などの外傷性損傷が考えられるそうです。また、赤みや熱感、発熱を伴う場合は化膿性関節炎などの感染性疾患が疑われることもあります。これらは早期の検査や施術が必要になることが多いため、我慢せず早めに医療機関へ相談することが勧められています(引用元:メディカルノート、Ubie、ねもと内科クリニック)。
腫れが長引く・他の関節にも症状がある場合
手首の腫れが数週間以上続く、あるいは指や肘、膝など他の関節にも腫れやこわばりが出ている場合は、関節リウマチや乾癬性関節炎などの自己免疫疾患が関与していることがあると言われています。これらの疾患は早期発見・早期対応が予後に影響する可能性が指摘されており、初期の段階から専門医による触診や血液検査、画像検査が行われることがあるそうです。また、リウマチ性多発筋痛症などは高齢者に多く、肩や股関節にも症状が広がるケースがあると言われています(引用元:ねもと内科クリニック、RAクリニック、メディカルノート)。
来院前に確認しておくとよいこと
医療機関に行く前に、症状が出た時期や経過、腫れが出るきっかけ、日常生活での不便な動きなどをメモしておくと、触診や検査がスムーズになると言われています。また、腫れの部位を写真で記録しておくことも、医師が経過を把握する助けになるそうです。
#手首腫れ #受診目安 #整形外科 #内科 #関節リウマチ
治療法とケア方法:疾患別に解説

手首の腫れへの対応は、原因となる疾患や症状の程度によって方法が異なると言われています。ここでは、一般的に行われる保存療法から専門的な施術までを整理します。
保存療法(安静、サポーター、アイシング)
軽度の炎症や外傷直後には、安静にして患部の負担を減らすことが基本とされています。日常動作で手首を酷使しないようにし、必要に応じてサポーターやテーピングで固定すると安定しやすいそうです。また、炎症が強い場合は氷や保冷剤をタオルで包み、1回15〜20分程度冷やすアイシングが有効とされます。これにより血流が一時的に抑えられ、腫れや熱感を和らげる効果が期待できると言われています(引用元:ねもと内科クリニック、メディカルノート、Ubie)。
薬物療法(鎮痛剤、ステロイド)
炎症や痛みが強い場合には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの鎮痛剤が使われることがあるそうです。関節リウマチや重度の腱鞘炎では、ステロイド注射によって炎症を抑える方法が選択される場合もあります。これらの薬は症状の軽減を目的としており、原因を直接改善するわけではないとされています。そのため、使用期間や量は医師の指示に従うことが重要と考えられています(引用元:ねもと内科クリニック、RAクリニック)。
専門的な治療(生物学的製剤、エコー検査、手術対応)
関節リウマチなどの自己免疫疾患に対しては、生物学的製剤による免疫反応の抑制が行われることがあると言われています。これらは長期的な関節破壊の予防を目的とするケースが多いそうです。腱鞘炎や靱帯損傷では、エコー検査によって炎症部位や損傷範囲を可視化し、より的確な施術計画を立てることが可能とされています。また、骨折や腱の断裂などでは、プレートやワイヤーを用いた手術が必要になることもあります。手術後はリハビリを通して可動域と筋力を回復させることが推奨されているそうです(引用元:メディカルノート、ねもと内科クリニック)。
#手首腫れ #保存療法 #薬物療法 #生物学的製剤 #手術対応
日常生活での予防とセルフケアのポイント

手首の腫れや痛みを防ぐためには、日々の生活習慣や動作の工夫が役立つと言われています。ここでは、手首を守るための具体的な方法を紹介します。
手首の使い過ぎを避ける工夫(作業姿勢・休息・ストレッチ)
長時間同じ作業を続けると、手首に負担が蓄積するとされています。パソコン作業や調理などで手首を酷使する場合は、1時間に1回程度は作業を中断し、軽く手首を回す・反らすなどのストレッチを取り入れるとよいそうです。
作業時の姿勢も重要で、肘と手首の高さが水平になるよう机や椅子を調整すると負担が軽減すると言われています。また、重い物を持つときは片手ではなく両手で支えるように意識すると、手首の腱や関節へのストレスを減らせるとされています(引用元:mediaid-online.jp、メディカルノート)。
スマホやパソコン操作の際の注意点
スマホの長時間使用は、手首や親指周囲の腱に炎症を起こすリスクがあると指摘されています。片手での操作を控え、机に置いた状態で両手を使うか、音声入力なども活用するとよいそうです。
パソコン操作では、キーボードやマウスの位置を体に近づけ、手首を反らしすぎないようリストレストを使用する方法も推奨されていると言われています。これにより手首の背屈角度が緩和され、腱や靱帯への負担を減らせると考えられています(引用元:メディカルノート)。
妊婦・更年期の女性へのアドバイス
妊娠中や更年期は、ホルモンバランスの変化や体のむくみにより手首の腫れや痛みが出やすいとされます。むくみが強い場合は、手首を心臓より高く上げて休むことや、手首周囲を温めて血流を促すことが有効とされています。また、手首の冷えは炎症を悪化させる可能性があるため、冷房の風が直接当たらないように配慮するとよいそうです(引用元:mediaid-online.jp、メディカルノート)。
#手首腫れ #予防 #ストレッチ #スマホ操作 #更年期ケア