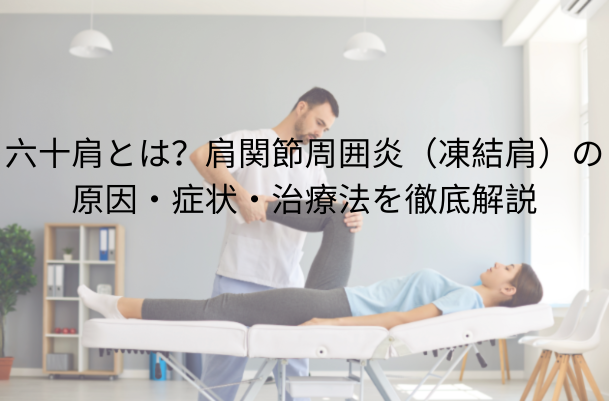六十肩とは?肩関節周囲炎・凍結肩の基礎知識

医学的名称と俗称の違い
六十肩は、肩関節の動きに関わる組織(腱、靭帯、関節包など)が炎症を起こし、痛みや可動域の制限が生じる状態を指す俗称です。医学的には「肩関節周囲炎」や「凍結肩」と呼ばれることが多く、特に60歳前後に症状が出やすいことから「六十肩」という呼び名が定着しています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
肩関節周囲炎と凍結肩の関係
肩関節周囲炎は、肩の関節包や周囲の組織に炎症が起こった状態を指します。炎症が長引くと関節包が癒着し、肩の動きが大きく制限される「凍結肩」に進行する場合があると言われています。凍結肩になると、日常動作で腕を上げたり後ろに回したりする動きが著しく制限され、生活の不便さを強く感じるケースがあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
発症のきっかけ
六十肩のはっきりとした原因はまだ解明されていないとされていますが、加齢による組織の変性や血流低下、過去の肩のケガや長期的な負担が要因の一部と考えられています。糖尿病や甲状腺疾患などの持病がある人は発症しやすい傾向があるとも報告されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
年齢との関係
「六十肩」という名前からもわかるように、発症年齢は60歳前後が多いですが、50代後半〜70代でも起こることがあります。また、40代で発症する場合は「四十肩」と呼ばれます。年齢に応じて呼び方は変わりますが、病態そのものはほぼ同じとされています。
注意点
痛みが続く、腕が上がらない、夜間痛がひどいといった症状がある場合は、放置せずに早めの対応が望ましいとされています。特に動かさない期間が長くなると、肩の拘縮(固まり)が進み、回復までに時間がかかる可能性があるといわれています。
#六十肩 #肩関節周囲炎 #凍結肩 #肩の痛み #加齢による症状
症状と進行ステージ:炎症期→拘縮期→回復期
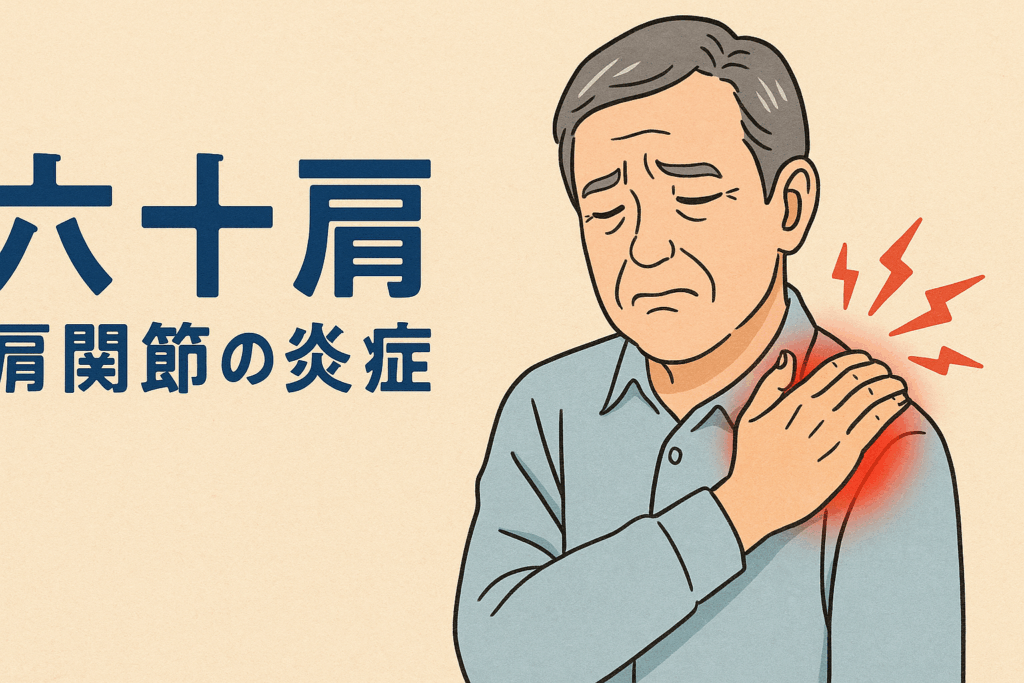
炎症期(急性期)
六十肩の初期は「炎症期」と呼ばれ、肩周囲の組織に炎症が生じて強い痛みが現れるとされています。特に動かしたときだけでなく、安静時や夜間にも痛みが出る「夜間痛」が特徴的で、眠りを妨げることもあります。可動域はまだある程度保たれていますが、痛みによって動かすのを避ける傾向が強まります。この時期は数週間〜数か月続く場合があると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
拘縮期(慢性期)
炎症が落ち着き始めると、「拘縮期」に移行すると言われています。この段階では痛みはやや軽減するものの、肩関節包や周囲の組織が硬くなり、動かせる範囲が大幅に制限されます。腕を上げたり後ろに回したりする動きがしづらく、日常生活の動作にも影響が出やすくなります。例えば、髪を結ぶ、背中に手を回す、服を着替えるといった動作で不便を感じるケースが多いと報告されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
回復期
最後の「回復期」では、拘縮していた関節や筋肉が少しずつほぐれ、動かせる範囲が広がる傾向があるとされています。日常動作の不便さも徐々に減っていきますが、改善のスピードには個人差が大きく、半年〜1年以上かかる場合もあるとのことです。この時期には、無理のない範囲で肩を動かすことが、機能の回復につながると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
症状の経過と注意点
これら3つのステージは必ずしも明確に分かれるわけではなく、症状が混在する場合もあります。また、炎症期に長く安静を続けると拘縮が進みやすいとも言われており、適切な時期に体を動かす工夫が大切と考えられています。夜間痛が続く、可動域が急激に狭まったといった場合には、自己判断せず早めに専門家へ相談することが望ましいとされています。
#六十肩 #炎症期 #拘縮期 #回復期 #夜間痛
原因と触診:加齢、炎症、他疾患との鑑別

加齢に伴う組織の変性
六十肩は、加齢によって肩周囲の組織に変性が起こることが一因と考えられています。具体的には、腱や靭帯、関節包の柔軟性が低下し、小さな刺激や負荷でも炎症が起こりやすくなると言われています。特に60歳前後では、長年の生活動作や仕事での負担が蓄積し、肩の動きを支える筋肉や腱に微細な損傷が発生しやすいとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
炎症の影響
炎症が起こると、関節包や周囲の滑膜が腫れ、痛みや可動域の制限につながります。この炎症は明確な外傷がなくても発生する場合があり、夜間痛や安静時の痛みとして現れることもあります。炎症期が長引くと、関節包が癒着し「凍結肩」と呼ばれる状態へ移行するとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
他疾患との鑑別
六十肩と似た症状を示す疾患は複数あります。たとえば、腱板断裂では腕を上げるときに特定の角度で強い痛みや力が入らないといった特徴が見られることがあります。変形性関節症では、関節軟骨の摩耗によって動作時の痛みやゴリゴリとした音が発生するとされています。さらに、石灰沈着性腱板炎では急激な痛みの出現が特徴で、六十肩と区別が必要とされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
触診と検査の流れ
肩の状態を確認するには、まず触診で可動域や痛みの部位を確かめることが多いです。そのうえで、X線やMRI、超音波などの画像検査を行い、骨や腱、関節の状態を詳しく調べるケースがあります。これにより、六十肩なのか、または他の疾患による症状なのかを見極めやすくなるといわれています。
#六十肩 #肩関節周囲炎 #加齢変化 #腱板断裂 #変形性関節症
治療・セルフケアの選択肢

保存療法の考え方
六十肩の対応では、多くの場合「保存療法」と呼ばれる方法が選択されると言われています。これは手術を行わずに、痛みの緩和や可動域の回復を目指す方法です。具体的には、リハビリやストレッチ、物理療法、ステロイド注射などが含まれます。炎症期には無理な動作を避けつつ、肩関節への負担を減らす工夫が推奨されることがあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
リハビリとストレッチ
炎症が落ち着いた拘縮期や回復期には、理学療法士や施術者の指導のもとでのリハビリが有効とされます。代表的なのは、関節の可動域を少しずつ広げるストレッチや、肩甲骨まわりの筋肉を鍛える運動です。自宅でできるセルフストレッチもありますが、痛みが強いときには控えめに行うことが望ましいとされています。
ステロイド注射の活用
痛みが強く、日常生活に支障が出ている場合には、医療機関でステロイド注射が検討されることがあります。これは炎症を抑える目的で行われる方法で、一時的に動かしやすくなるケースがあると言われています。ただし、回数や間隔には制限があり、専門家の判断のもとで行う必要があります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
夜間痛への対処法
六十肩では夜間痛が続くことで眠りの質が下がり、回復に影響する場合があります。枕やクッションを使って肩を高めに支える、横向き寝の際に痛い方を上にするなど、寝姿勢の工夫が有効とされています。また、就寝前に温めて血流を促すと痛みが和らぎやすいとも言われています。
理学療法の具体例
物理療法には、温熱療法、低周波治療器、超音波治療器などがあり、血流改善や筋肉の緊張緩和を目的に行われます。これらは施術者の管理のもとで行うことが推奨されており、状態に合わせて組み合わせることで回復を助ける可能性があります。
#六十肩 #保存療法 #リハビリ #夜間痛 #理学療法
予防と再発防止:日常生活でできること

肩の柔軟性を保つストレッチ
六十肩の予防や再発防止には、日常的なストレッチが役立つと言われています。特に肩関節の前後・上下の動きを意識し、無理のない範囲で動かすことが大切です。たとえば、壁に手をつきながら少しずつ腕を上げる「壁歩き運動」や、タオルを両手で持って背中の上下で引っ張る「タオルストレッチ」などは、自宅でも行いやすい方法として紹介されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
姿勢改善の重要性
肩の動きは背中や首の姿勢と密接に関係しています。猫背や巻き肩の状態が続くと、肩関節にかかる負担が増え、可動域が狭まりやすいと言われています。日常生活で背筋を伸ばす意識を持つこと、デスクワーク中はこまめに立ち上がって肩を回すなど、姿勢を保つ習慣づくりが予防に役立つと考えられています。
急な運動の注意点
運動不足の状態で急に激しい運動を行うと、肩の筋肉や腱に負担がかかりやすくなります。特に重い荷物を持ち上げる動作や、急に腕を大きく振る動きは注意が必要とされています。運動を始める際は、軽いストレッチやウォーミングアップから取り入れることで、ケガや炎症のリスクを減らせる可能性があります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3838/)。
生活習慣との関係
肩の柔軟性や筋力は、日々の生活習慣の積み重ねで変化します。買い物袋を片手で持ち続けない、洗濯物を干す高さを工夫するなど、肩に偏った負担がかからないようにする意識も予防策のひとつとされています。
継続のコツ
予防や再発防止のための運動や姿勢改善は、短期間では大きな変化を感じにくい場合があります。しかし、数週間から数か月続けることで徐々に肩の可動域や動かしやすさが変わってくると言われています。無理のない範囲で日々の生活に取り入れることが、長期的な健康維持につながります。
#六十肩 #予防 #ストレッチ #姿勢改善 #運動習慣