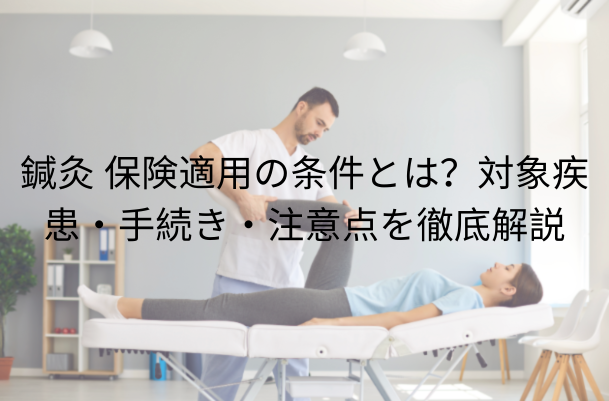鍼灸は保険適用できるの?基本ルールを理解しよう
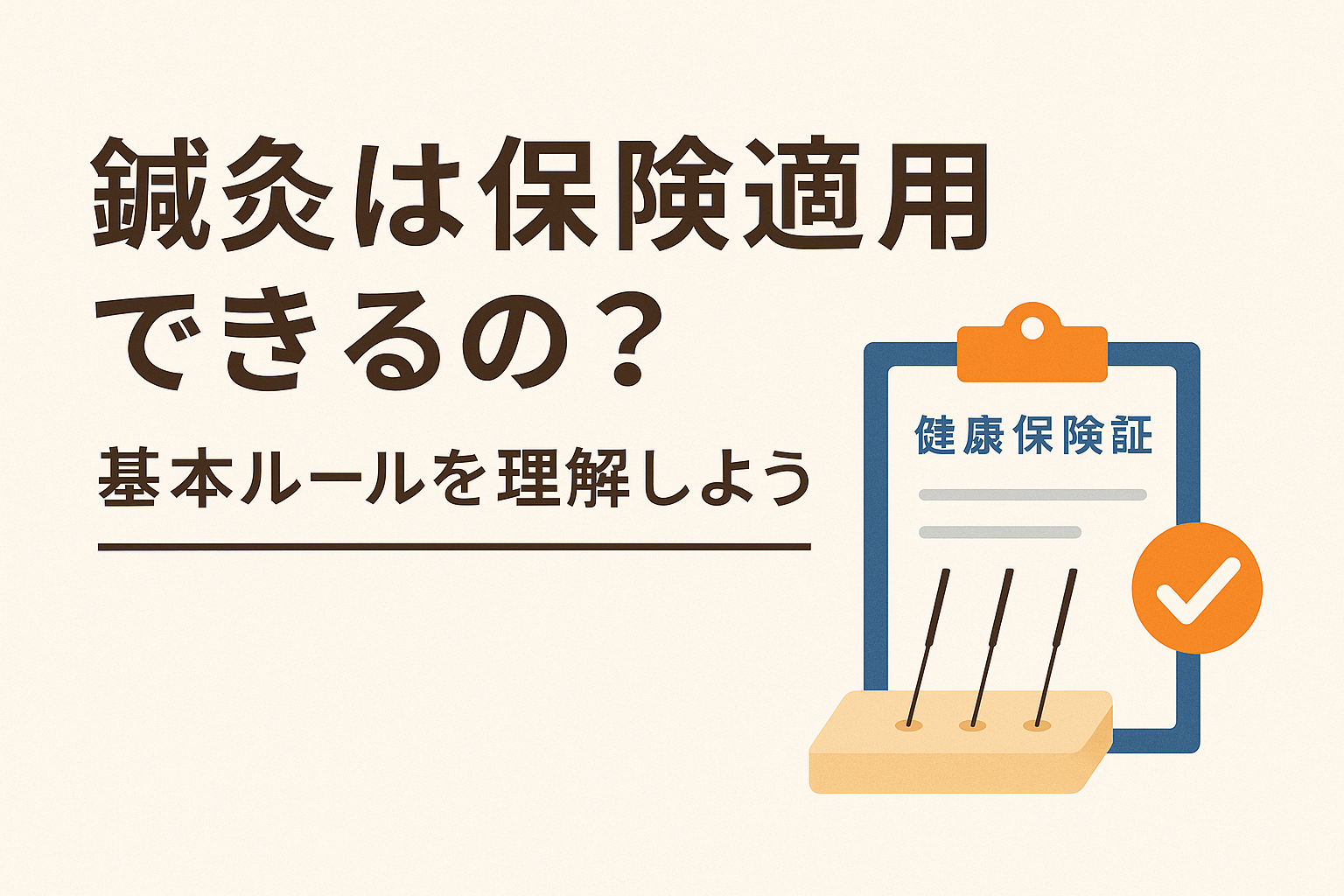
そもそも「鍼灸に保険が使える」ってどういうこと?
「鍼灸って保険きくの?」と疑問に思ったことがある方は少なくないはずです。実は、鍼(はり)や灸(きゅう)による施術は、条件を満たせば健康保険を使える場合があると言われています。自由診療が一般的なイメージのある鍼灸ですが、医師の「同意書」があることで、特定の症状に限り保険適用となる制度が存在しています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。
ただし、すべての施術に対して自動的に保険が使えるわけではなく、以下のような基本的なルールが設けられています。
保険適用に必要な条件とは?
まず、厚生労働省が定める6つの特定疾患に該当している必要があります。対象となるのは、たとえば「神経痛」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「リウマチ」「頸椎捻挫後遺症」など、いずれも慢性症状であるケースが多いです。
そして最も重要なのが、医師による「同意書」の発行が必須という点。これは、医療機関での検査や経過観察を受けたうえで、「鍼灸での施術が妥当」と判断された場合に交付されます。つまり、「自己判断で保険適用になるわけではない」ということになります。
また、整骨院や整体との違いもよく混同されがちですが、それぞれ保険の対象となる施術や条件は異なるため、事前に確認しておくと安心です。
自由診療との違いを整理しておこう
自由診療では施術内容や時間配分に幅があり、比較的柔軟な対応が可能とされています。一方、保険適用となる施術では、あらかじめ定められた範囲内での対応になるため、症状や目的によってどちらが適しているかは異なるようです。
保険で受けられる範囲に限りがあるぶん、自由診療を組み合わせて対応するケースも見られます。そういったハイブリッドな施術方針についても、来院前に相談できると安心につながるでしょう。
#鍼灸保険適用
#医師の同意書が必要
#対象疾患に注意
#自由診療との違い
#制度の基本ルール理解
保険適用の対象となる疾患一覧
どんな症状が対象になるの?
「鍼灸って保険が使えるって聞いたけど、全部の症状が対象になるわけじゃないの?」と疑問に思っている方も多いかもしれません。実際には、厚生労働省が定めた6つの疾患に該当する場合のみ保険適用が検討されるとされています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。
その6つとは以下のとおりです。
- 神経痛(例:坐骨神経痛、肋間神経痛 など)
- 頸腕症候群(首から腕にかけてのしびれ・痛み)
- 五十肩(肩関節周囲炎)
- 腰痛症(慢性的な腰の痛み)
- リウマチ(関節リウマチの症状緩和目的)
- 頸椎捻挫後遺症(いわゆる「むち打ち」のような症状)
これらは慢性の経過をたどることが多く、医師の同意を得てから鍼灸施術が保険適用となる場合があるとされています。
「慢性的な症状」がポイントとされる理由
対象疾患を見てもわかる通り、いずれも急性ではなく、慢性症状に対しての施術であることが共通しています。これは、継続的な経過観察や日常生活での不快感に対してアプローチする目的が大きいからです。
たとえば、「腰が慢性的に痛い」「肩の動きが年々悪くなってきた」という方は、医師と相談のうえで同意書をもらい、鍼灸を選択肢として検討することができるかもしれません。
保険適用されないケースに注意
一方で、肩こりや単なる疲労回復などは、保険の対象外とされています。これは、医療的な必要性や慢性的な病態と見なされないためです。また、美容鍼やスポーツコンディショニングなども同様に自由診療扱いとなります。
「なんとなく疲れているから」「気分転換に鍼を受けたい」というケースでは保険は適用されないことが多いため、目的や症状を事前に明確にしておくことが大切です。
#鍼灸保険対象疾患
#慢性症状への対応
#神経痛と五十肩
#腰痛の保険利用
#対象外ケースに注意
実際の保険適用までの流れと必要書類

保険を使うためのステップを確認しよう
「鍼灸って保険がきくって聞いたけど、どうやって使えばいいの?」という疑問、よくありますよね。実際には、医師の「同意書」取得をはじめとする一定の手続きを踏むことで、鍼灸施術に健康保険を使える場合があると言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。
以下は、基本的な流れの例です。
- 医療機関(内科や整形外科など)で触診を受ける
- 鍼灸による施術が妥当と判断された場合、「同意書」を発行してもらう
- 鍼灸院にその同意書を持参し、保険申請の手続きを行う
この一連の流れを踏むことで、保険適用が検討されるようになると言われています。もちろん、事前に鍼灸院側に相談しながら進めるのが安心です。
必要な書類と注意点について
最も重要なのが**「同意書」**です。これは病院やクリニックの医師が「この方には鍼灸が有効かもしれない」と判断したうえで発行するもの。つまり、医師の協力があってはじめてスタートできる制度です。
このとき、必ずしもどの医療機関でも発行してもらえるわけではありません。「うちでは書けない」と断られるケースもあります。ですので、事前に“鍼灸の同意書をお願いできますか?”と確認しておくのがスマートです。
また、同意書には**有効期限(通常3ヶ月)**があるため、継続して保険を使いたい場合は定期的に更新手続きを行う必要があります。更新時も再度医師の確認が必要です。
#鍼灸保険の流れ
#同意書の取得方法
#医師の協力が必要
#必要書類と更新期限
#保険申請の具体的手順
自己負担額や費用の目安はどれくらい?
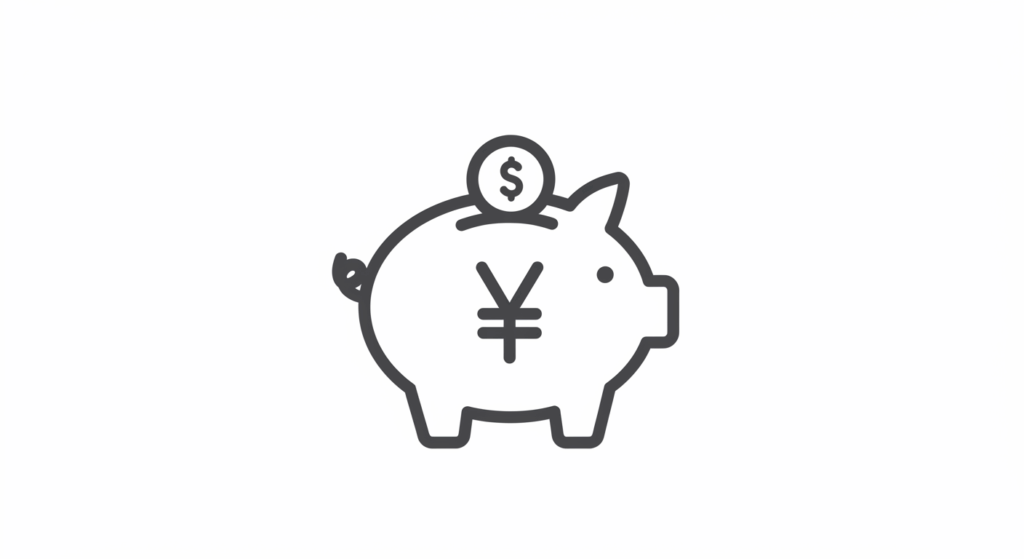
保険適用時の自己負担割合とは?
「鍼灸って保険が使えるって聞いたけど、実際にいくらぐらいかかるの?」と気になる方は多いはずです。鍼灸が健康保険の対象となる場合、費用の一部は保険でまかなわれ、残りが自己負担になるとされています。
一般的には、会社員や公務員の方であれば3割負担、後期高齢者医療制度を利用している方であれば1〜2割負担になるケースが多いようです。たとえば施術料が1回2,000円だった場合、3割負担なら600円程度が自己負担になる、というイメージです。
ただし、施術内容や地域、取り扱っている鍼灸院の方針などにより金額は前後するため、事前に確認しておくことが安心につながると言われています。
初回と継続で費用が変わることも
初診時には、問診や触診、施術方針の説明などに時間をかけるため、初回のみ費用が高めになる傾向があります。保険適用でも、初回は1,500円〜2,000円前後、2回目以降は500〜1,000円前後になることが多いようです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。
また、自由診療を併用する場合はその分費用が上乗せされることもあります。「○○の施術は保険が使えますが、△△は自由診療扱いです」と案内されるケースもあるため、不明な点は気軽に確認してみましょう。
事前に費用感を確認しておくと安心
保険を使えるからといって全額が補助されるわけではなく、ある程度の出費があることは理解しておいたほうが安心です。鍼灸院によっては、料金表をホームページで公開しているところもありますので、来院前にチェックしておくとスムーズです。
「実際にかかる費用っていくらくらいですか?」と直接問い合わせてみるのも良いでしょう。無理なく継続できる範囲で利用するためにも、費用の見通しを立てておくことが大切です。
#鍼灸保険の費用
#自己負担割合の仕組み
#初回料金と継続費用
#自由診療の上乗せに注意
#費用確認で安心通院